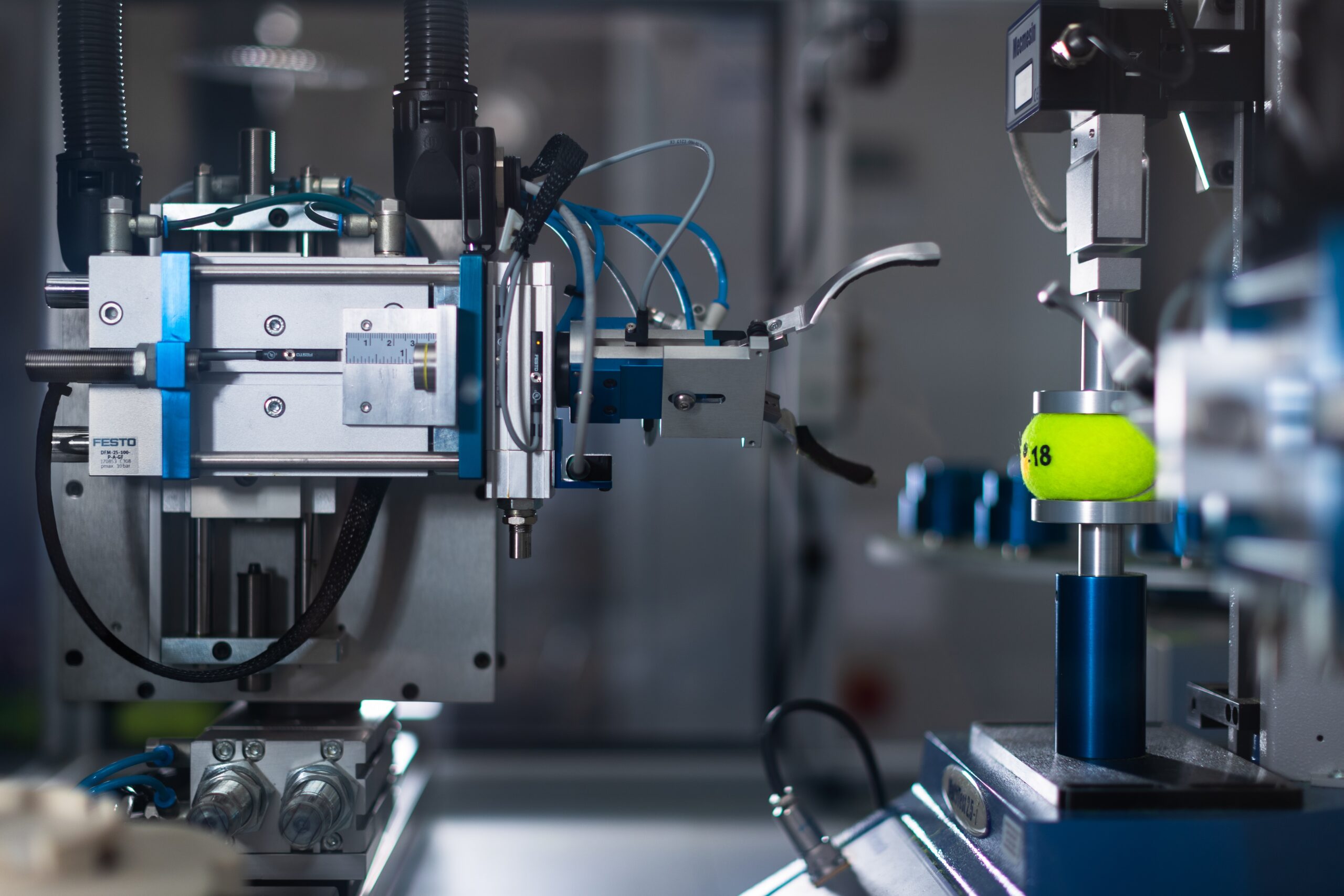カーヴァーの短編の中で、「象」はマイランキングのかなり上位に入るくらいに好きな作品だ。かなり気の毒な状況に追い込まれた中年男の話ではあるのだが、どこか喜劇的で読後に少し元気になれたりもする。
「象」は1986年刊行の「ザ・ニューヨーカー」に掲載された短編で、原題はElephant。カーヴァー作品を少しでも読んだことのある人なら、動物の「象」の話ではないことは未読でも想像がつくだろう。象は主人公の夢に少し出てくるだけだが、シンボリックに使われている気もするので、他のカーヴァー作品ほど不思議な印象は受けない。むしろ、深みや味わいがあってなんとなく好きなタイトルだ。
この作品の時代背景である80年代後半は、アメリカが構造不況に陥っていた深刻な時期。それが作品に影を落としてはいるのだが、ありのままの現実を労働者目線で多くの人に伝えようといった意義や信条的なものは感じられない。時代の陰鬱な空気を踏まえて読む方が良いが、作品自体はもっと個人の内面に寄ったものだと思う。
主人公の「私」は、母親に毎月仕送りを続けている。失業中の実弟にせがまれ大金を貸してもいる、返ってこないと知りつつ。別れた妻には裁判所が決めた額を月々送金している。食うに困る生活を続ける実の娘と2人の孫にも金銭的な援助をし、ニュー・ハンプシャーの大学に入った息子にも金を送っている。とにかく経済的に苦しい状況だ。前述した通り、不況の真っ只中ではあるのだが、社会的な弱者やブルーカラーの実態を如実に描いているのかというと、全然そうではない。それどころか、揃いも揃って同情できるような人物ではない。主人公の「私」以外は金の無心をするばかりで、自ら汗をかいて何とかしようとする意思を持っていない。口先で調子の良いことや嘘を重ね、自分の不運を誇示するばかり。死に物狂いで働こうとしないのだ。自分の生活を切り詰めて金銭を工面し続ける「私」への不義理も平気で重ねる。金蔓として利用しているようにさえ思える。
読書中、ずうずうしく何度も金をせびる人間たちに何度も怒りを覚えた。どうして厳しい態度に出ることなく、相変わらず金を送り続けるのかという疑問が膨らむ。おそらく、読まれた方の多くが似たような怒りや疑問を感じたのではないだろうか。
この短編の鍵はおそらくそこにある。
主人公の「私」は、荒れた生活をしていた昔の自分を時々振り返る。野蛮だったかつての自分を思い出す。夢に見たりもする。アルコールへの嫌悪をつぶやくシーンもある。つまり、以前の「私」はどうしようもないダメ男で、親しい人間たちを裏切り、傷つけていたことがそこから想像できる。親兄弟、妻、子供たちは、「私」の犠牲者なのだ。皆にお金を送り続けるのは、償いの行為ととれる。「私」が支払うべき当然の代償であり、簡単に償えるものではない。そもそも文句を言える立場ではないのだ。全てを放り出して地球の裏側に逃げることなど到底できやしない。背負ったまま走り続けるしか選択肢はない。そう考えるとこの話は腑に落ちる気がする。
風を切って駆けるラストシーンは素晴らしい。「男なんてそんなものさ」と言っているようで、何度読んでもなぜか笑えてくる。