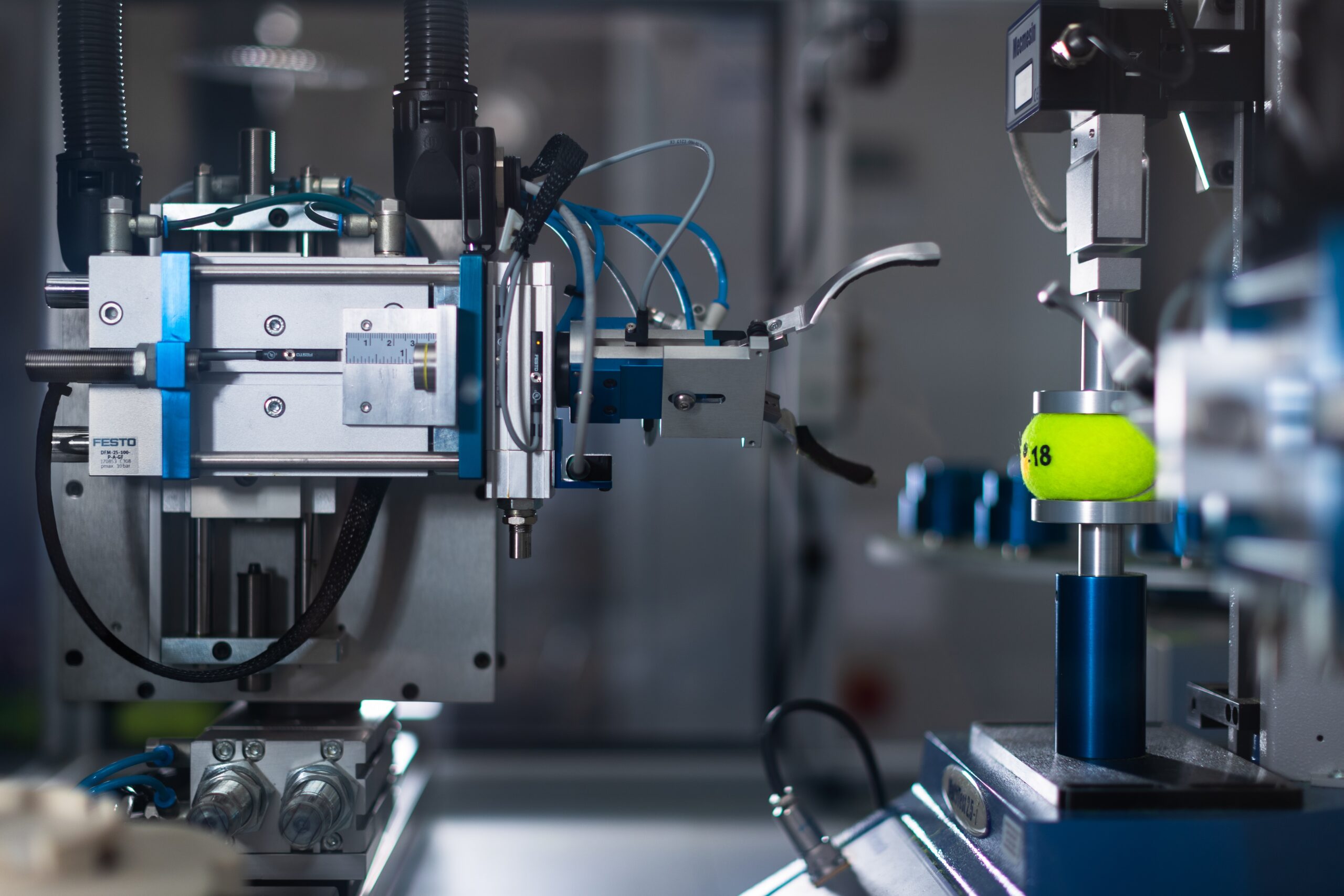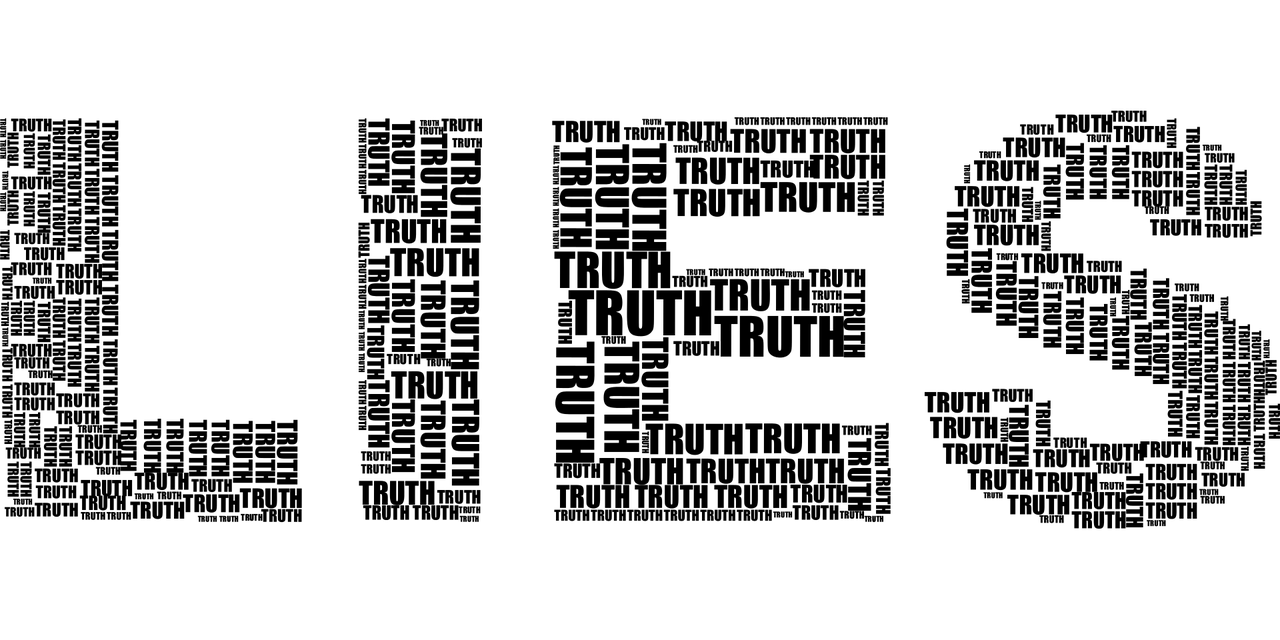主人公の男のしていることは取り乱していて見苦しいけれど、その心情が手にとるように伝わってくる。
この短編に登場する夫婦は、すでにその関係が壊れてしまっている。夫のバートは家を出て独りで生活している。妻のヴェラには新しいボーイフレンドがいるが、バートはまだヴェラのことも家のことも吹っ切れずにいる。どうしても現実を受け入れることができないのだ。
まるで歓迎されていないのに、妻の元を連日訪ねるバート。そして、知らぬ銘柄のタバコの吸い殻や、何度もかかってくる「チャーリーはいますか?」という電話に嫉妬する。(この電話はチャーリーという男がこの家で長い時間を過ごしていることを意味している) アル中で破壊的な行為を繰り返してきたバートは、またしても平静を失い、電話のコードをナイフで切断してしまう。そして思い入れのある陶器の皿を持って家を出ていく。
崩壊前の幸せな頃の象徴である陶器の皿を持ちながら、クルマのギアをバックに入れるというエンディングなのだが、これはバートが前に進むことができず、過去を振り返っていることのメタファーである。別の男性と新しい人生へ歩み出そうとしているヴェラとは真逆であり、そのコントラストがとても遣る瀬ない。
印象的なのは、物語の後半、妻のヴェラが「裁判所の接見禁止命令を絶対に取るからね!」とコードを切断された電話機をどすんと置いて怒鳴るシーンがある。その時、電話機が「ちゃりん」という音を立てるのだが、これはバトル開始のゴングを意味している。二人の関係に決着をつけるべく戦闘モードに入った瞬間がとても巧みに表現されている。
この短編にはまるで希望が無いように思えるが、ある種の加速主義的な解放への予感はある。落ちるところまで落ちれば、次に展開するしかない。訳者の村上春樹氏は「一人の男が腹をくくる前の空白」と後書きに書いているが、そういう意味では「終わりは始まり」という微かな光を感じ取れなくもない。
カーヴァーの短編には、痛みを知る人の優しさが滲み出ている。そして何より理屈抜きに面白い。読めば読むほど好きになっていく自分がいる。
愛について語るときに我々の語ること (村上春樹翻訳ライブラリー)