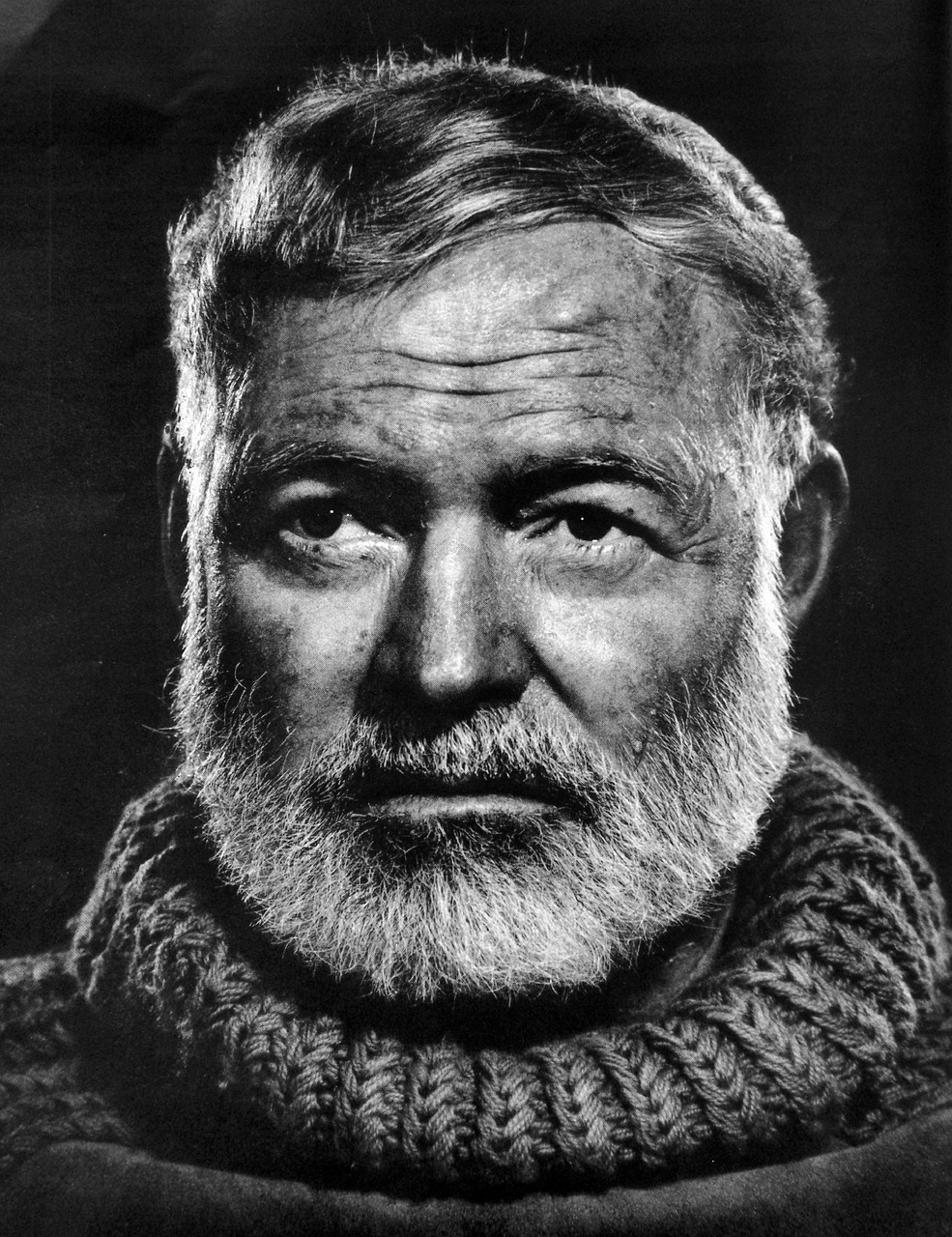1936年の中編で、同年には「世界の首都」や「キリマンジョロの雪」も発表されている。乗りに乗っていた時期と見る人もいるが、実際はどうなのだろう?「世界の首都」は個人的に傑作と思うが、「キリマンジョロの雪」は直情的でやや深みに欠ける。絶好調と呼べるかは別にして、創作意欲に溢れていた時期であることだけは間違いないだろう。
「フランシス・マカンバーの短い幸福な生涯」に関しては、まずタイトルで損をしている気がする。文学的な匂いはするものの、アフリカを舞台にしたライオンやバッファローを狩る激しい話であることがイメージしにくい。日本人にはフランシスが男性であることすらピンとこないのではないだろうか。
邦題を批判しているのではなく、原題のThe Short Happy Life of Francis Macomberがどうもイマイチという気がする。The Short Happy Lifeにはどこか間の抜けた雰囲気があり、読む意欲をあまり喚起されない。
「老人と海」「海流の中の島々」「キリマンジャロの雪」のようにタイトルは魅力的だが、そこまでクオリティが高くない作品も多いので(あくまで私の主観ではあるが)、小説は読んでみないとわからないということだ。
読後には「短い幸福な生涯」が何を指しているのかに気づかされ、考えさせられる。著者の「生」や「幸福」の捉え方が、このタイトルに端的にあらわれていることを知る。
「フランシス・マカンバーの短い幸福な生涯」は、著者のアフリカ旅行の狩猟ガイドを勤めたフィリップ・パーシヴァルから聞いた「ライオンを目の前にして気が動転した客」の話からインスピレーションを得たらしい。
手負いのライオンを前に怖気づいて逃げ出してしまった臆病者の夫、すっかりそれに幻滅してしまった妻、妻を寝とる狩猟経験豊富なガイド、そして弾を喰らったライオン。場面ごとに視点をコロコロと変えながら物語が進行していく。やや奇妙なスタイルに思えるが、ある種の立体感といったらよいのか、多層感といったらよいのか、粒立ちの良さを個人的には感じた。
衝撃的なラストシーンについての解釈だが…
古典なのでネタバレを気にせず書こうと思ったが、やはり未読の人のために触れずにおこう。
ちなみに、ヘミングウェイとアフリカ旅行を共にしたのは2番目の妻ポーリン・ファイファー。裕福であり、ジャーナリストであり、敬虔なカトリックの信者である。(ヘミングウェイもカトリックに改宗) 二人は1927年5月に結婚し、1940年11月に離婚した。ヘミングウェイは離婚3週間後に3人目の妻と再婚している。(凄いね)
ポーリンは、息子グレゴリーの逮捕とヘミングウェイとの電話での激しい口論により、1951年に56歳でショック死したと言われている。後に医者となったグレゴリーが、ヘミングウェイとの電話が死因であると怒りをぶちまけた。(悲しすぎる)
「フランシス・マカンバーの短い幸福な生涯」は描写に迫力があり、読み物としては面白い。まあまあ長いが退屈な読書にはならない。でも、言ってしまえば幼稚な男の幼稚なエピソードである。わがままで、包容力がなく、判断力に欠ける。そうした大人になれない男性がリアルに描かれている。勇気とは何か?生きるとは何か?といった重要な主題がそこにあるとも言えなくはないが、くだらないこだわりと感じる人も少なくない気がする。
(↑こういう正直な記事って、あまりネット上にない。もちろん賛同できない人も多いとは思う。低レベルな解釈と笑う人もいるかと思うが、自分の言葉で書いていることだけでも評価していただけると嬉しい)
仕事が山積しており、深掘りする気力が湧いてこないので、今回はここらへんで締めようと思う。好き勝手に感想を書き散らかしたが、いろいろと考えるきっかけをくれた短編であった。