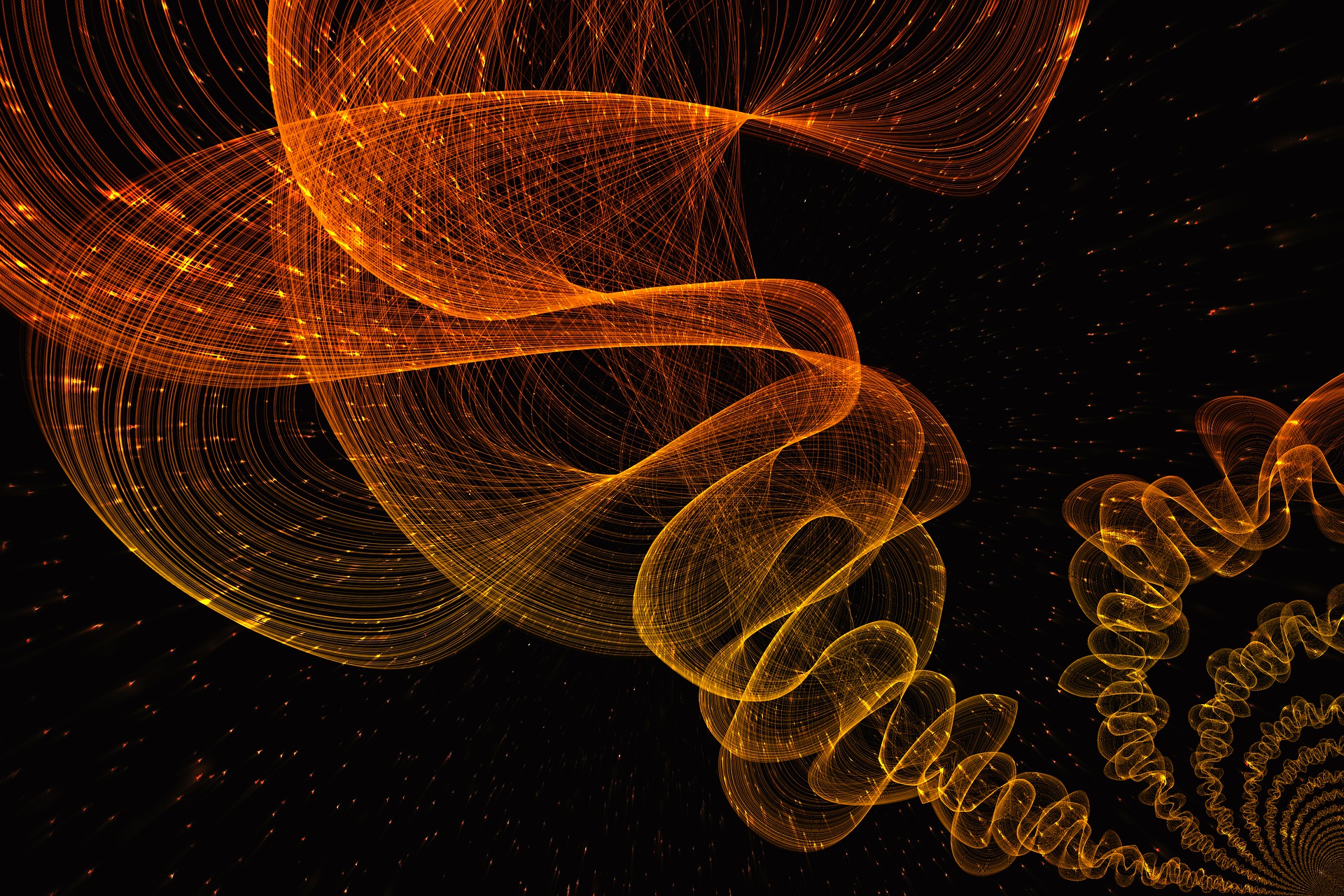まず、何と言っても邦題が良い。
原題は「I Could See The Smallest Things」で、訳者である村上春樹氏はクセの強い奇妙なタイトルに首を傾げているが、個人的には好きなタイトルだ。わかりやすいかは別として、どこか哲学的(?)で惹かれる。
夜中に外で物音がするのでローブのまま表に出てみると、妻を亡くし仕事も辞めてしまった隣人がクレンザーでなめくじを退治している。言ってしまえば、それだけのどこかしら気味の悪い話だ。心の平衡感覚を乱すようなダークさに作品全体が覆われている。増殖するなめくじが、病みつつある精神を象徴している
印象に残ったのは、頭上を旅客機が通り過ぎる短いシーン。主人公の中年女性は、機内で読書をしたり、地上を眺めたりする乗客たちの様子をふと想像する。上空と地上のコントラスト、それが明暗を強調するスパイスとして効いている。
カーヴァーはこの手の闇を書かせたら右に出る者が居ない名手とは思うが、再生への意思とか脱出への光とかはまったく描かない。ヘミングウェイの場合、主人公が苦境に立たされていても、どこか風が通っていて、明日は明日の風が吹くと思わせてくれる開放性がある。カーヴァーにはそれがなく、行き止まりの息苦しさに包まれている。
小説にポジティブさを求めても、まるで応えてくれないタイプの作家だ。それでも、切り取られたリアルな現実は、絵空ごとの希望よりずっと存在感があって沁みてくる。夜の匂いや音、風の湿り気まで高精細で喚起され、生の手触りをそこに得ることができる。
愛について語るときに我々の語ること (村上春樹翻訳ライブラリー)