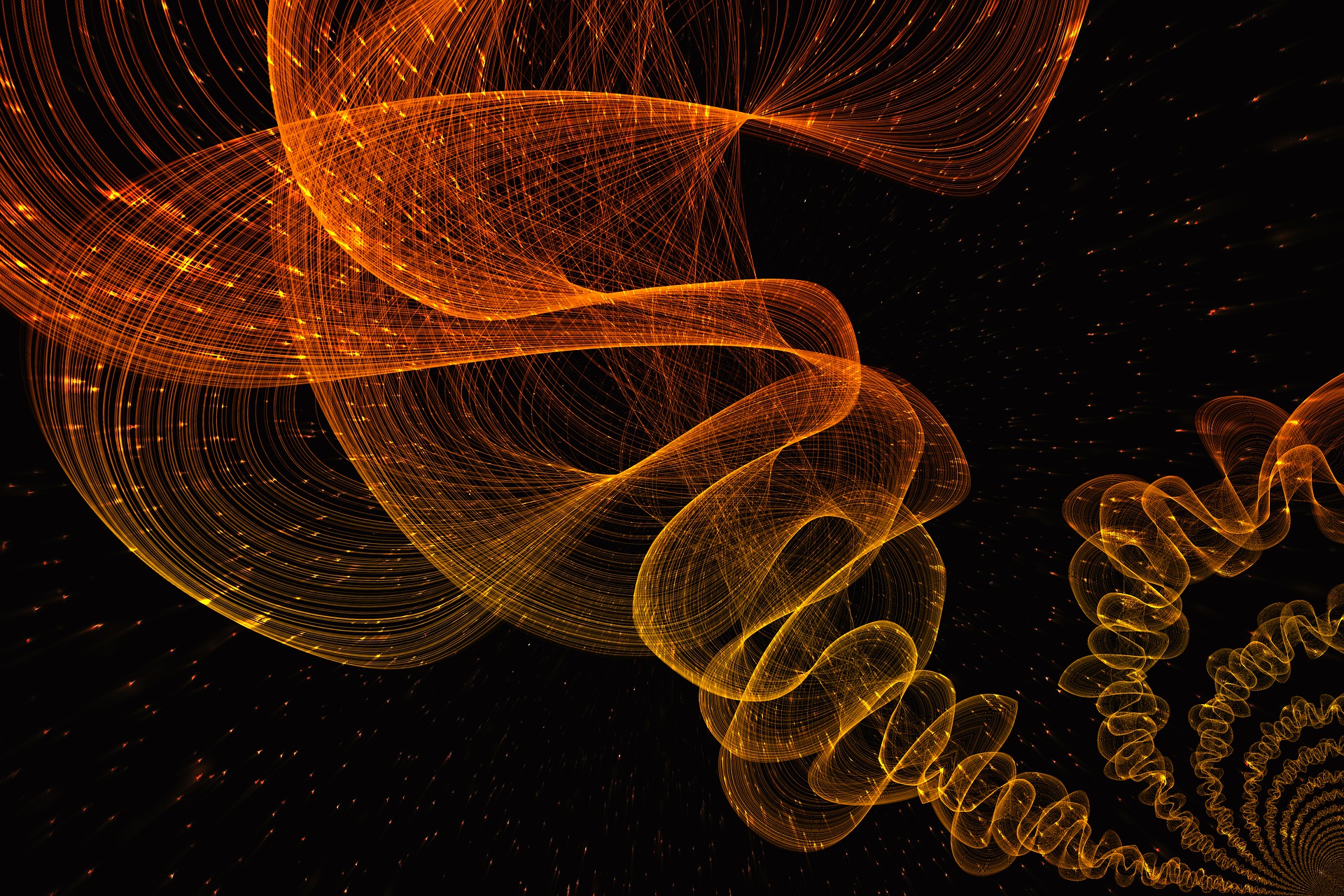四年前に別れて、すでに別の男性と再婚している元妻の家を、前もって電話することもなくいきなり朝9時に訪ねる「私」。もちろん、歓迎されるはずはない。元妻は積年の鬱憤を晴らすかのように「私」を責め立てる。二人は思い出を懐かしむ関係にはない。
「こんなことを言って気を悪くしてほしくないんだけど、私は時々あなたを銃で撃って、あなたがのたうつところをじっと見ていられそうな気がするの」
元妻はそこまで言う。「あなたどこか別のところにいなくちゃならないんじゃないの?」と問われ、「私」は「別に行くところがない」と答え、彼女のドレスの裾にしがみつくように両膝をつく。昼食を食べに夫が帰宅する前に、元妻は「私」に帰えるよう促す。
一体、男は何が目的で元妻を訪ねたのか。未練なのか。辛さからなのか。理由は語られず、男の態度もはっきりとしない。元妻が困惑するのも当然のことだ。大抵の男はこうした行動には出ないし、相手の気持ちを考えれば行けるはずもない。それが、新しい家族と暮らす家であればなおのことだ。しかし、この男は訪ねて行ってしまう。レイモンド・カーヴァーの私生活を題材にした実話なのだろうか。であれば、相当に厳しい精神状態だったことがうかがえる。自ら奈落の底に飛び込むような行為は、よほど切羽詰って自暴自棄でなければ実行にまでは至らない。想像するほどに切なくて、とても苦しい短編だ。このような題材で書くのだから、ある意味でとてもタフな作家とも言える。普通の人間なら辛すぎて向き合えないだろう。カーヴァーは、怖い。