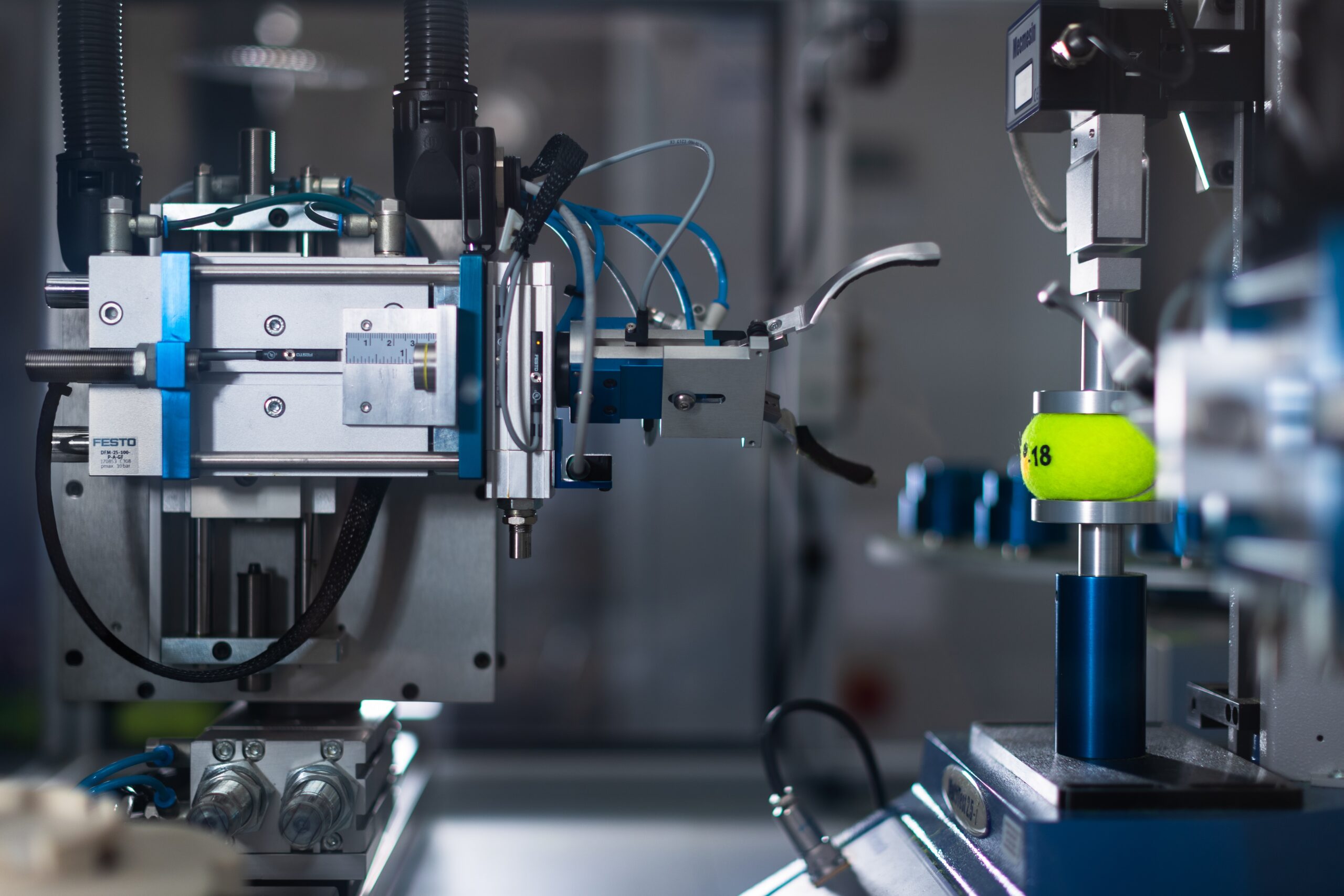1987年、「ニューヨーカー」に掲載された短編。原題はErrandで、邦題の「使い走り」とか「用事」といった意味。多くのカーヴァー作品同様に、視点を中心から少しスライドさせたようなユニークで印象的なタイトルだと思う。
よく知られたことなのであまり書きたくはないが、「使い走り」の執筆時、カーヴァーは自らが癌であることを知らされていた。この作品は、作家が気力を振り絞って書いた最後の短編だ。
作品の中心にあるのは「死」であり、カーヴァー作品としては珍しく、自らの経験をベースにしたものではなく、ロシアの作家チェーホフの死に際を描いている。アンリ・トロワイヤの「チェーホフ伝」に強く感じるところがあり筆を取ったそうだが、近づきつつある自らの最期を重ねているのは間違いない。作品自体は、「実際に起こった出来事から逸脱するわけにはいかない」と伝記に記載された情報を元に書いたようだ。
カーヴァーは、チェーホフに影響を受けている。二人の共通点は、訳者である村上春樹氏のあとがきに詳しいので短くまとめてみた。
・功成り名を遂げた高名な短編小説作家であった。
・エリート階級の出身ではなく、サロン的な芸術に背を向けた。
・生き方や小説のスタイルが極めて個人的で、時流とは無縁な場所にいた。
・病により比較的若くして世を去った。
・中年になって良き伴侶を得て、温かく看取られた。
このように作風だけでなく人生に於いて共通点が多い憧れの作家の死に、カーヴァーが自らを重ねたのは自然なことに思える。これは「使い走り」という短編の凄みでもあるのだが、けっして死を美化しているわけではない。正直な感想として、チェーホフの妻や臨終に立ち会った医師の言動には心に響くものがなかった。むしろ、やや高慢さを感じたりもした。
素晴らしいのはホテルのボーイで、その存在は作品の中で際立っている。無垢さ、軽さ、明るさ、弱さ、優しさが入り混じった若いボーイが、とても澄んで愛らしく思えた。ここでは詳細を書かないが、最後の場面でその若いボーイがある行動を取る。何気ないその行動が不思議なほど印象に残る。そのアイデアを思いつき、カーヴァーに提案したのは妻のテス・ギャラガーだという。生涯最後の短編のラストに妻のアイデアを採用したのだ。
チェーホフは1860年生まれのロシアの短編小説家(劇作家でもある)だが、当時のロシアでは「長編こそ小説」という風潮が強く、チェーホフのように短編を発表し続けた作家は他にいなかった。今の時代も、短編は暇つぶしの軽い読み物として下に見る傾向は変わっていない気がする。私のように短編小説に強い思い入れがある人間にとっては、短編小説作家として生きたチェーホフとカーヴァーはいつでも特別な存在だ。