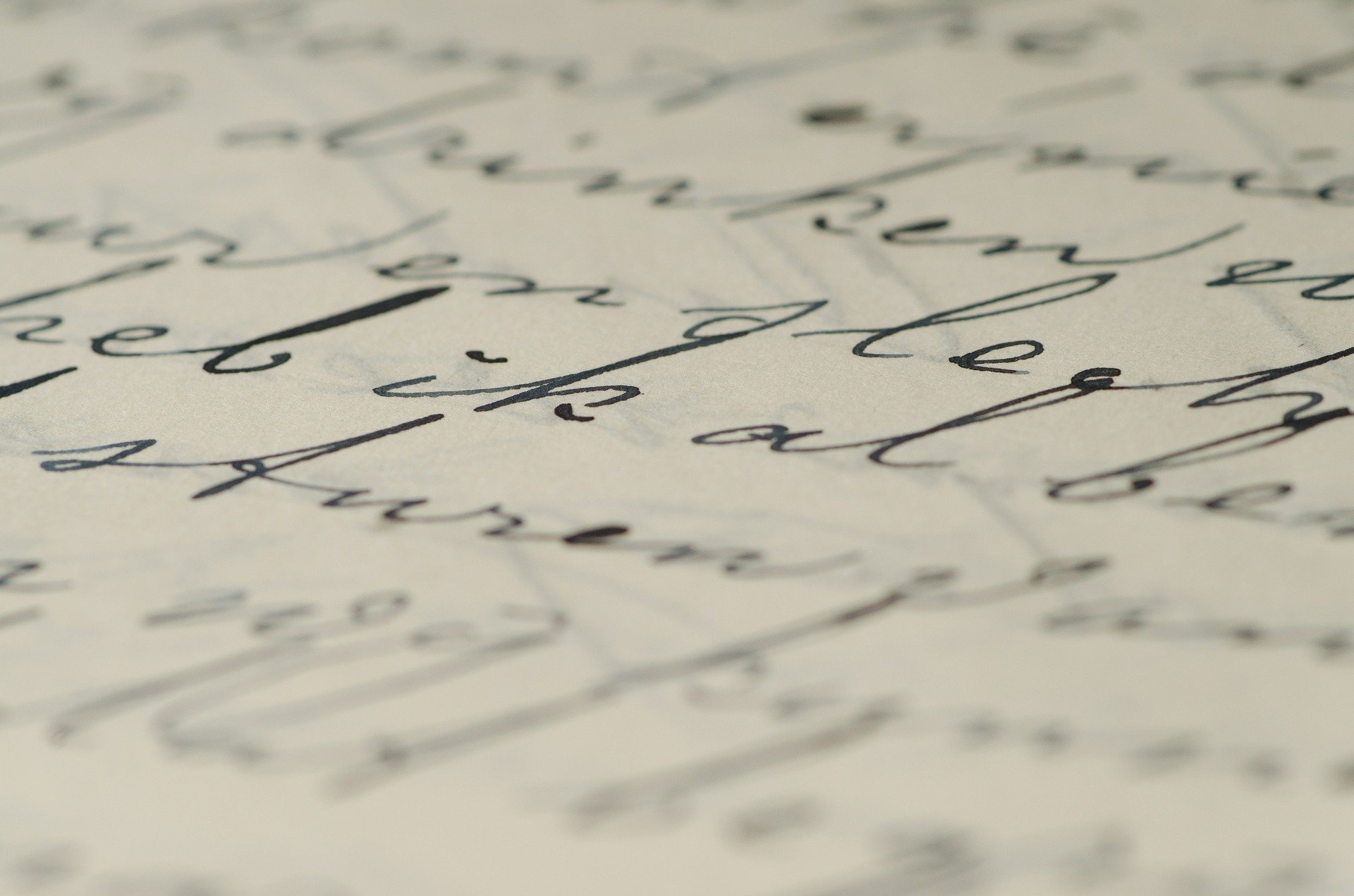この文体の涼しさや清々しさは何だろう。決してハッピーな話ではないのだが、疲れが取れるような気持ち好さがある。訳者のセンスの良さもあって、他の作家で得られない澄んだリアリティを愉しむことができる。他の作家どころか、映画、音楽、テレビ、YouTube、どこにもヘミングウェイの代わりになるものは見当たらない。少なくとも私の中では入れ替え不可能な魅力がそこにある。
「世界の首都」というタイトルから立ち上がるイメージと違い、主人公はマドリードのペンションでアルバイトをしている一人の少年。彼は闘牛士に強い憧れを抱き、日頃から獰猛な牛と闘う空想に耽っている。同じペンションで働く年下の少年に、実際に牛の角を見たらきっと怖気づくと揶揄され、感情をあらわにそれを否定する。絶対に恐れたりしないと言い張る。そこで二人は椅子の足に二本の包丁をまきつけ、勇敢さを試す危険な実験をはじめる。
衝撃的なラストは書かないことにするが、読後に強い余韻を残す物語だ。(「衝撃的なラスト」とかも書いちゃだめだよね。でも、新作でなく古典なので許してちょーだい)
この短編は、少年を主人公としながらも、グランドホテル形式の群像劇として書かれている。つまり複数の人物を並行して描く、アンサブル・キャストと呼ばれる手法を採っている。それが功を奏しており、さまざまな闘牛士たちの盛衰やペンションの雰囲気がノンフィクションのようにリアルに伝わってくる。描写がベタッとしていなくて実に気持ちが好い。
個人的な好みもあるが、この作品に流れている空気が堪らなく魅力的だ。文章を書いていると、いつの間にか味が濃くなったり、雑味が混じってしまうものだが、著者は自ら厳しい基準を設け、数え切れないくらいに推敲を繰り返し、そうした余分なものを削ぎ落としていたのだと思う。余分なものが含まれていると、そこから腐敗していくので時間が経つと読めたものじゃなくなる。ヘミングウェイの作品は一世紀の時を経て、まだ充分な鮮度を保っている。本当に凄いことだと思う。