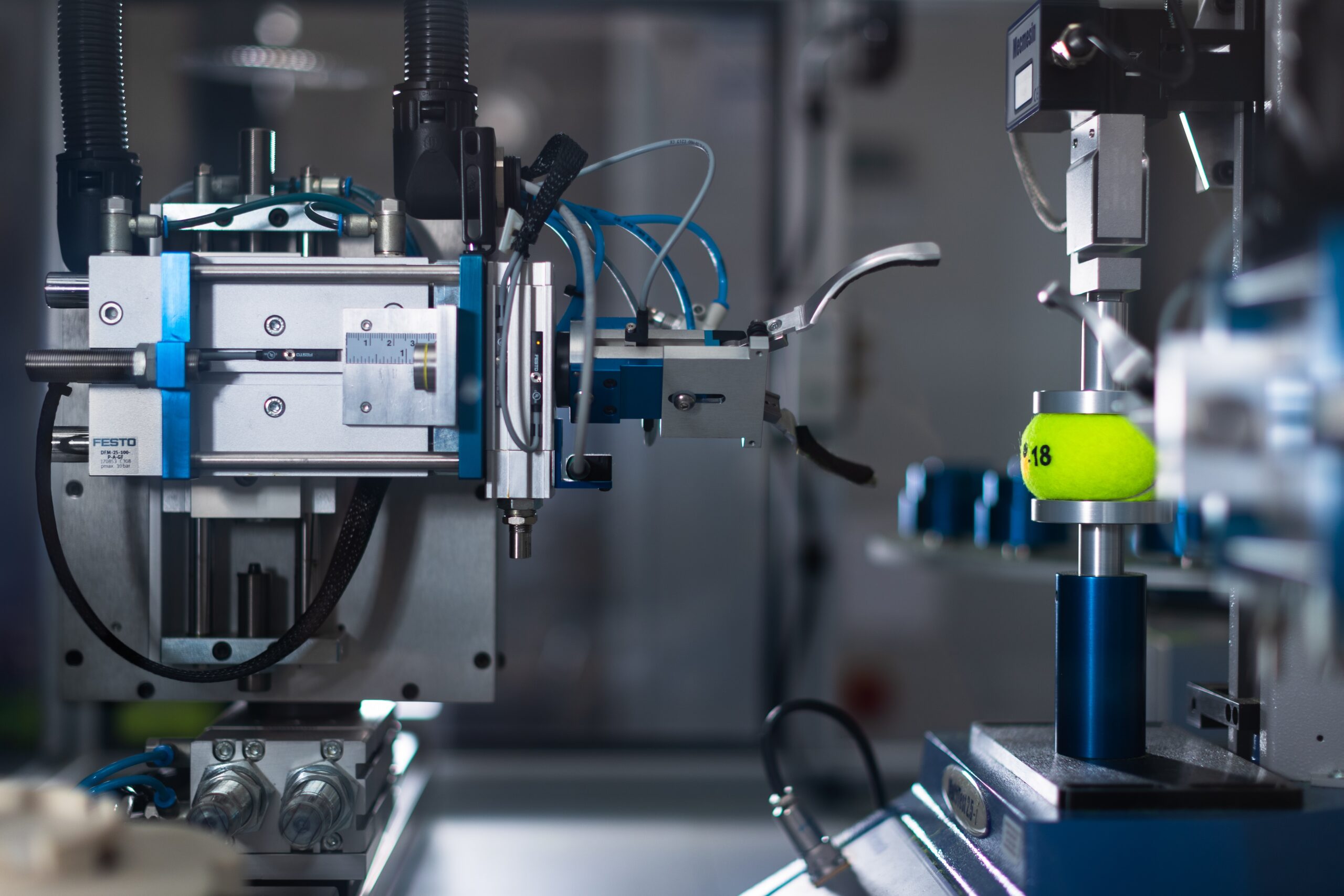久しぶりにカーヴァーを読んだ。わかりやすいし、読みやすい。持ってまわった言い方や堅苦しい言葉が使わていないため、疲れている頭にもすっと話が入ってきた。文学するゾと肩に力の入った小説は、正直なところ今は面倒くさい。最初の数行で放り出してしまうかもしれない。(ちょっと疲れが溜まっている)
それにしても、電車で本や雑誌を読む人をほとんど見なくなった。SNSやYoutubeなどキャッチーで刺激的なメディアに囲まれた時代だからこそ、選択肢として小説が生き残るためには「わかりやすさ、読みやすさ、短さ」が不可欠な条件ではないかと思ったりする。
「引越し」はとても読みやすいが、内容が軽い訳ではなく、そこには人生の悲哀が原寸大で描かれている。原題はBoxes。(Boxの複数形はBoxsでなくてBoxesと中学1年で習ったのを思い出した) ここでの箱は、引っ越しの段ボールのことだ。
数え切れないほど幾度も引っ越しを繰り返し、あらゆることに愚痴をこぼしてばかりいるネガティブ思考の母親。そして中年の息子と彼の恋人という3人が織りなす地味なホームドラマのような短編だ。ドラマといってもドラマチックな盛り上がりはなく、ラストも「えっ、これで終わり?」と声に出てしまうほど力が抜けている。
物語は息子の一人称で書かれている。この息子は、カーヴァー作品に頻繁に登場する、優しいところはあるが頼りなくて冴えない男だ。話自体もいい意味でぐだぐだしており、カーヴァーテイストを堪能できる。ただ、このぐだぐだ感には妙にリアリティがあるので、段々とやるせなさに息苦しくなってくる。(カーヴァー作品の多くがこの症状を誘発する)
カーヴァーの短編は充分に面白いのだが、同時にこの世界に長く浸っていてはいけないという警告が自分の内側から発せられる。中年になれば誰もが抱えている世知辛さやくたびれ感が全編に漂っているが、主人公には気持ちをリセットして前を向くとか、現状を変えようと汗をかくとか、そうしたガッツのようなものがまるで無い。だから、積極的にカーヴァー最高!とはならないが、気がつけば何となく手にとってしまう不思議な魅力を備えた作家だ。・・・何でだろう。