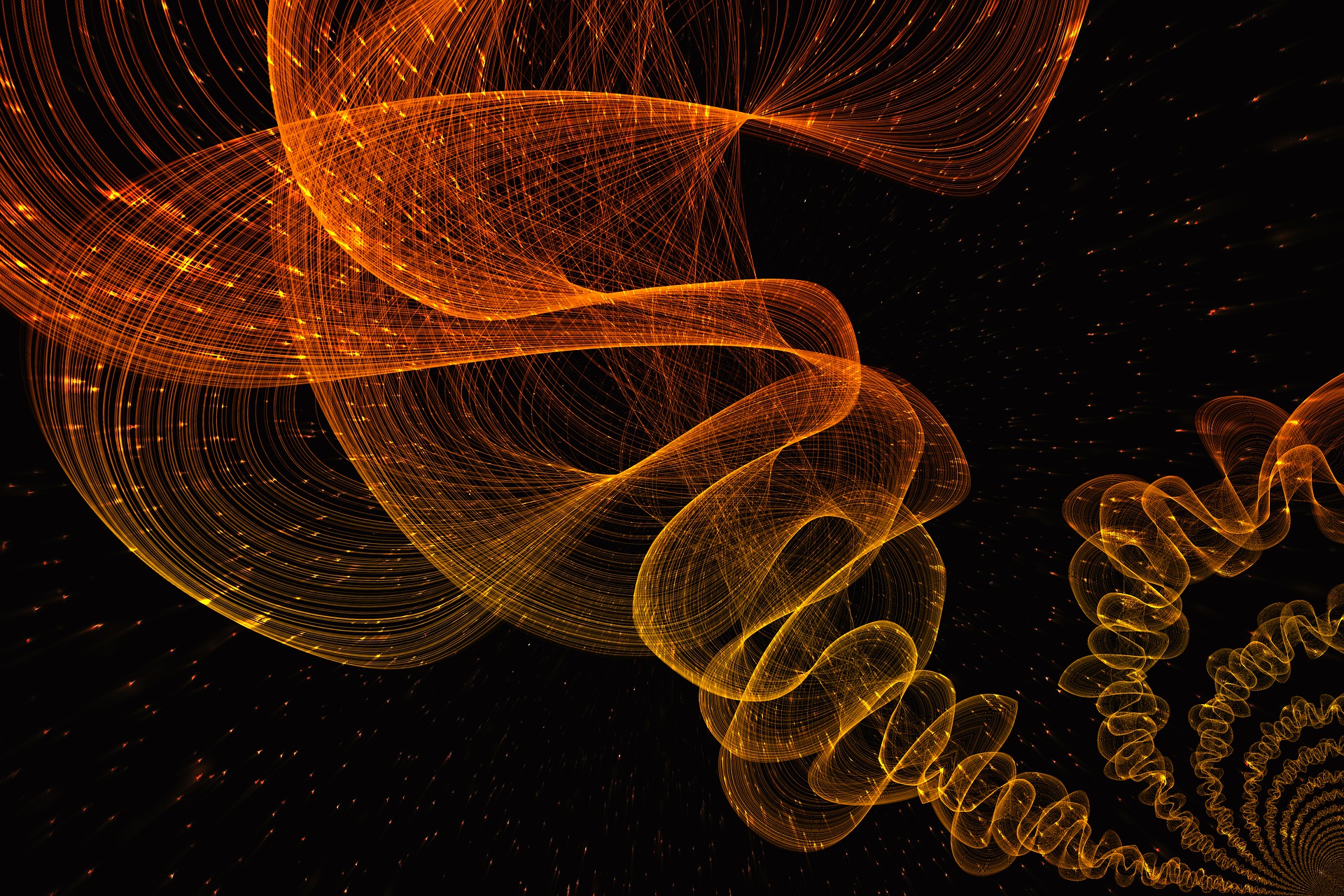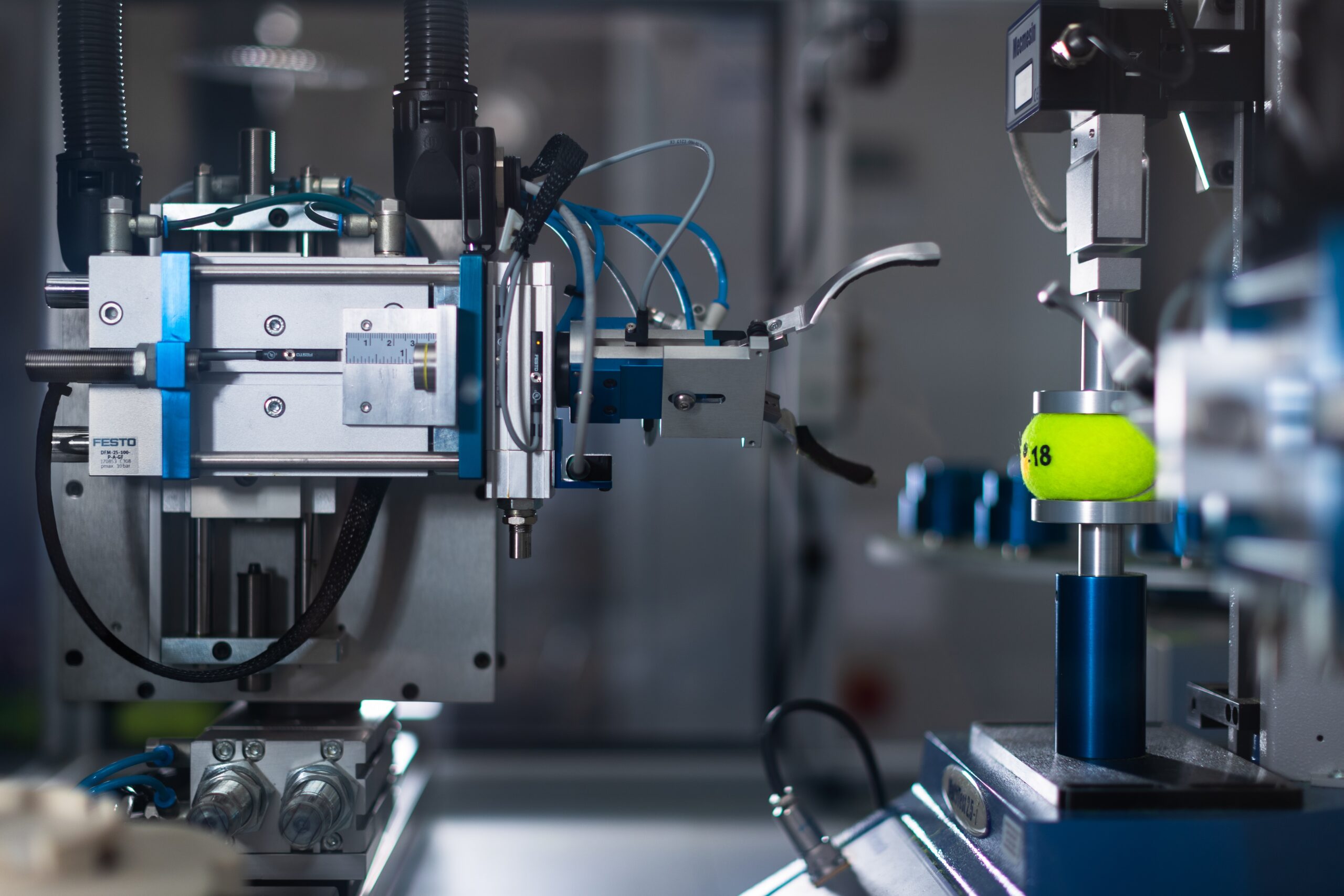夜遅く、この1986年初出の短編を読みながら、鳥肌が立つほどの不気味さを感じた。例のごとく奇妙なタイトルと思っていた「誰かは知らないが、このベッドに寝ていた人が」(原題:Whoever Was Using This Bed)は、読後に「生と死を別つ境界」を連想させ、恐ろしく暗い心の闇を浮かび上がらせる。
深夜の間違い電話、妻が語る奇妙な夢、もうもうとしたタバコの煙、そぼ降る雨、死を想起させる夜明け前の会話。そうした暗示的な描写に悪寒が止まらず、陰鬱さに息が詰まるような短編だ。しばらくは再読したいと思わないが、なかなか忘れることもできないだろう。他の方にとっては大袈裟に聞こえるかもしれないが、トラウマになりそうだ。 読書の怖さと同時に、不安を描くことに長けた作家の表現力を体感した。
カーヴァーの作品に登場する男女は、いつも至近で触れ合っているような親密さがある。そうした距離感はヘミングウェイの描き方とは明らかに異なる。人懐っこいというか、甘えたような感じが生理的に自分はちょっと苦手だったりもする。「どこか変な夫婦だな」と感じることも多く、小説の主人公たちの言動に感情移入できなかったりもする。そうしたズレや緩みのようなものが、他では得られない味わいなっているのも事実だ。