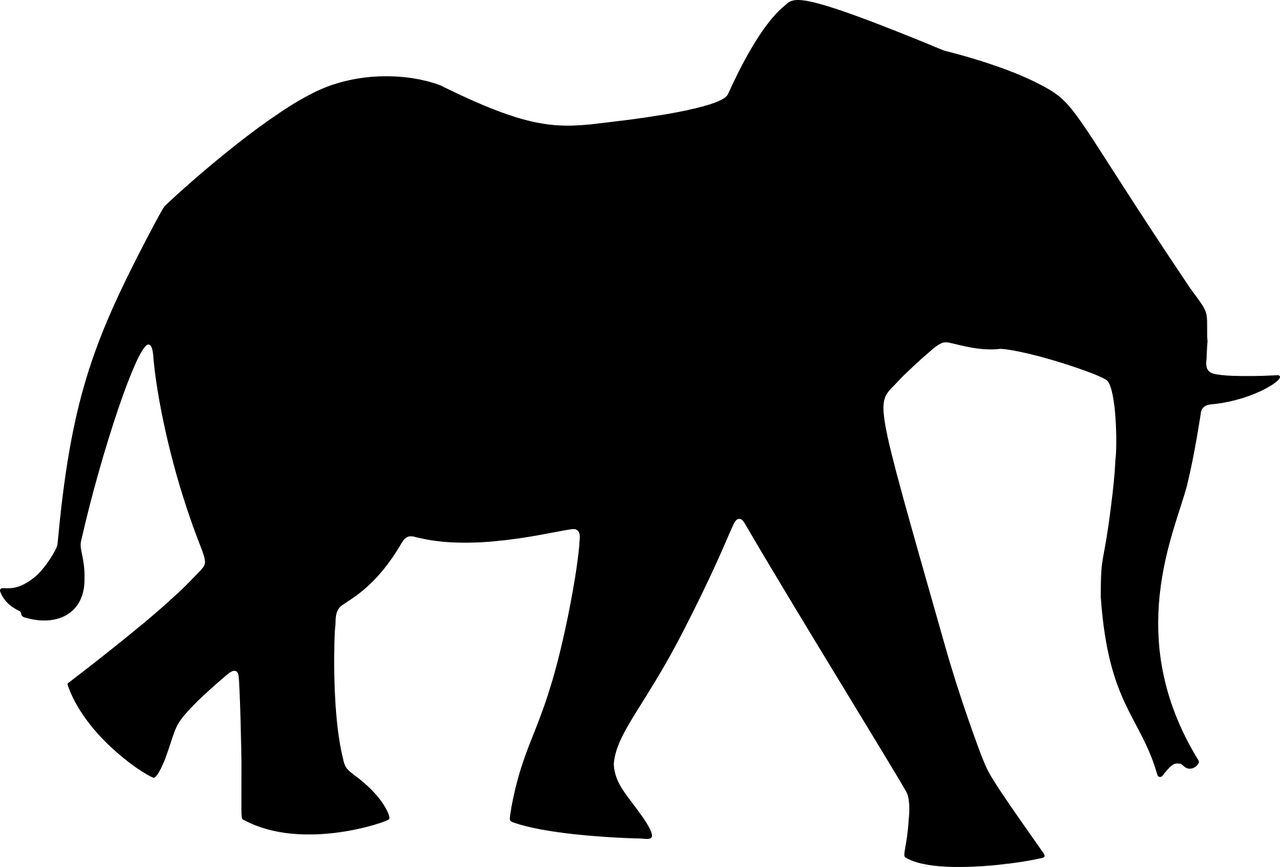今更説明するまでもないが、「中国行きのスロウ・ボート」 は村上春樹の初短編である。
今回、私が読んだのは大幅に加筆修正されたものかもしれない。詳しいことは知らないので、読んだものの感想を率直に書こうと思う。
初期作品ではあるが、村上春樹らしく語り手の「僕」と読者の距離がとても親密だ。本質を避けるというか、どことなく逃げていくような文体で、話の輪郭やコアをつかまえにくい。それでも、落ち着いたトーンと、アンニュイだけど魅力的なエピソードに引き込まれてしまった。スタイリッシュだし、著者が若いだけあって創作への熱量も感じる。良し悪しでなく、最近の作品よりきめ細かく書き込まれているという印象を受けた。
この短編では人生の中で出会った3人の中国人との記憶について、章を分けるカタチで描いている。断片的にエピソードが語られるため、一読しただけでは全体像をつかむのは難しい。物語の中心も見つからない。つながっているような、そうでもないような、触れられそうでいて、触れられない…。何度も何度も繰り返し読む人が多い短編のようだが、その気持ちもよくわかる。
そもそもは、ソニー・ロリンズが演奏するA Slow Boat to Chinaが好きで、「中国行きのスロウ・ボート」というタイトルだけ先に決まっていたらしい。(著者自身がそう語っている)
つまり、具体的な物語の設計図が頭にあったわけではなく、ひらめきで書きはじめ、あとは流れの中で生まれてきたものを磨いていった感じだろうか。この短編のように、良い小説って直感とかフィーリングに牽引されて書かれたものが多い気がする。ノートにプロットなどびっしり書き込んで練りに練って書く作家もいるが、がんじがらめの不自由さがあって、結果的に退屈なものになりがち。緻密だけど生命感がない、そういう小説はすぐに捨ててしまいたくなる。誰とは言わないが…。
「中国行きのスロウ・ボート」は理屈(思考)に縛られていないので、作りものの閉塞感がなく、鬱々した話であるのにどこか大らかだ。
今回の記事も浅い感想になってしまったが、語り手が核心を避けているところがあり、脳震盪のエピソードや教師の訓示、逆回りの電車などの解釈は自由度が高い。(読もうと思えば、どんな風にでも読めてしまう) 人はどこにいたって異端であり、土地や周囲の人々との違和感は消えない。だから相対的なことに左右されず、絶対的なものを軸にして生きていこう。私はそんな風に勝手にポジティブに解釈した。
この作品のムードは、ソニー・ロリンズの演奏から受けるリラックスしたものとはやや違っていた。せつなくて、やるせなくて、モノトーンの虚無感が漂っている。静かな雨の日のようで、私は嫌いではない。