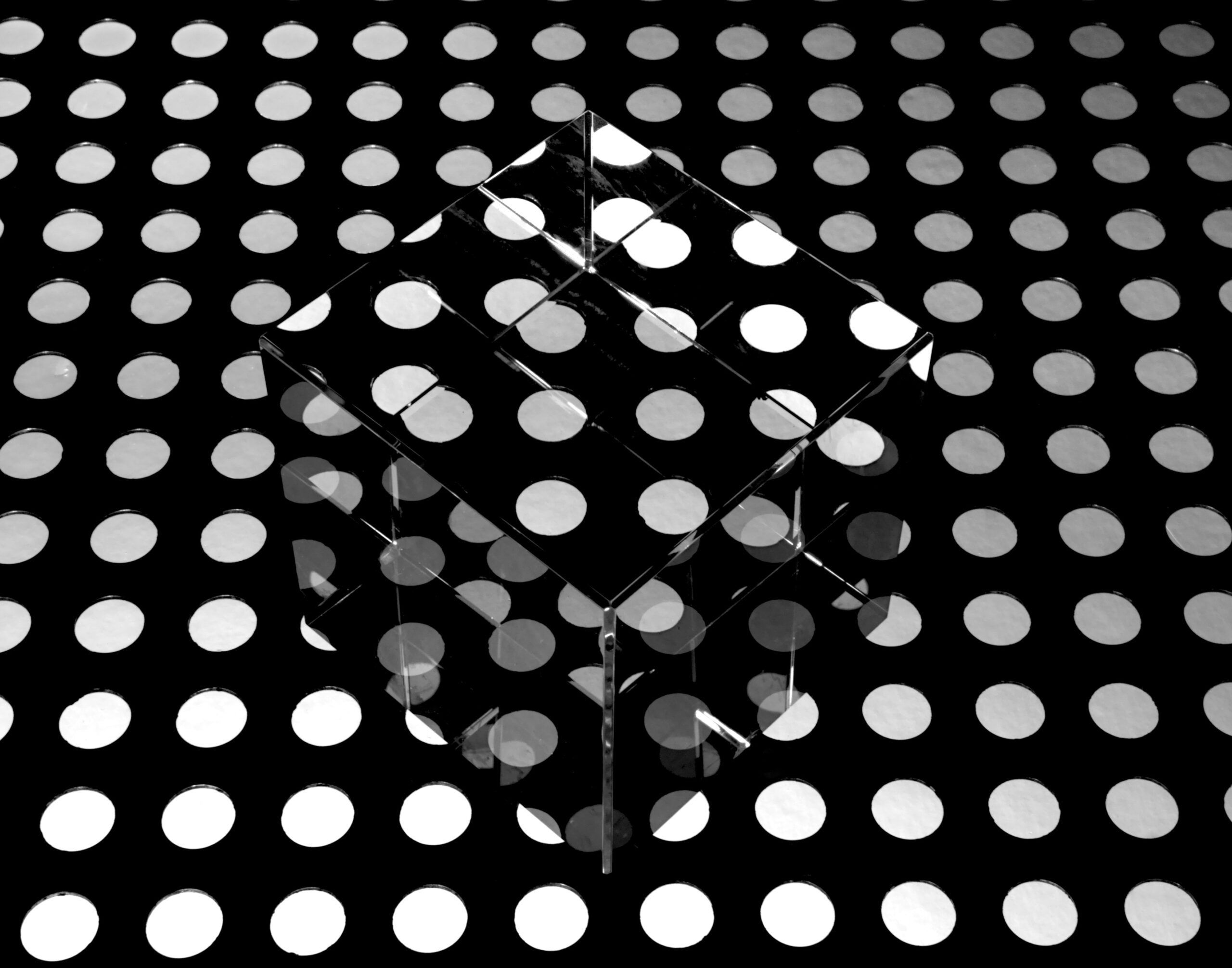村上春樹作品についての解説や解釈は、ネット上に読み切れないほど溢れているので、ここでは肩肘張らずに思いつきレベルの個人的な感想を少しだけ書こうと思う。(多くの方がすでに読んでいるという前提であらすじは省略)
「トニー滝谷」は、「孤独」をテーマにした短編とよく言われるが、果たして本当にそうなのだろうか?捉え方として自然だというのはわかるが、何だかどうも釈然としない。「孤独」についての表現が多く出てくるから、イコール「孤独」をテーマにした作品です、という感じにやや違和感を覚える。(ひねくれ者ななだけかもれないが) 戦争を舞台にしたロマンスや、老いを扱ったコメディなどのように、テーマが舞台の後ろに隠れていることはよくある。特に村上春樹作品の場合は。では、なぜ孤独が主題ではないと思うのか。読み返していて、引っかかったのは次の箇所だ。
イラストレータになったのも自然のなりゆきだった。実際の話、それ以外の可能性を考慮する必要もなかった。まわりの青年たちが悩み、模索し、苦しんでいるあいだ、彼は何も考えることなく黙々と精密でメカニックな絵を描き続けた。それは青年たちが権威や体制に対して切実に暴力的に反抗していた時代であったから、その極めて実際的な絵を評価するような人間は彼の周囲にはほとんど存在しなかった。美術大学の教師たちは彼の描いた絵を見ると苦笑した。クラスメイトたちはその無批評性を批判した。しかしトニー滝谷にはクラスメイトたちの描く「思想性のある」絵のどこがいいのかさっぱり理解できなかった。彼の目から見れば、ただそれは未熟で醜く、不正確なだけだった。
(あくまで個人的な感想ではあるが)上記の箇所に、この短編のコアがあるように思える。「実際性」と「思想性」の対比である。死んだ妻が残した服の山、死んだ父が残したレコードの山。それらは肉体を伴わなければ、煩わしさをもたらすだけの暗く遠い影に過ぎない。それは、未熟で醜く、不正確な影だ。「思想性」を嫌い軽視し、「実際性」を重んじる著者の感性が、「トニー滝谷」書かせたのではないだろうか。。。平たく、「フィジカル」と「メンタル」という言葉に置き換えても良いかもしれない。
ご存知の通り、「トニー滝谷」は著者のファンである市川準監督によって、映画化されている。脱色された映像に坂本龍一の奥ゆかしいピアノが溶け、原作の持つ心地好い非現実感や繊細さを観ていて感じた。西島秀俊のナレーションは、良し悪しの問題ではなく原作とはやや違う印象を受けた。原作が「要するに」とか「そんなわけで」といった割とフランクで闊達な語り口であるのに対し、映画のナレーションは穏やかで中性的なムードが強い。主演のイッセー尾形は、もう言うことがないくらいに良かった。もし自分が映画監督だったら全作品をイッセー尾形で撮りたくなるだろう、そこまで思ったほどだ。