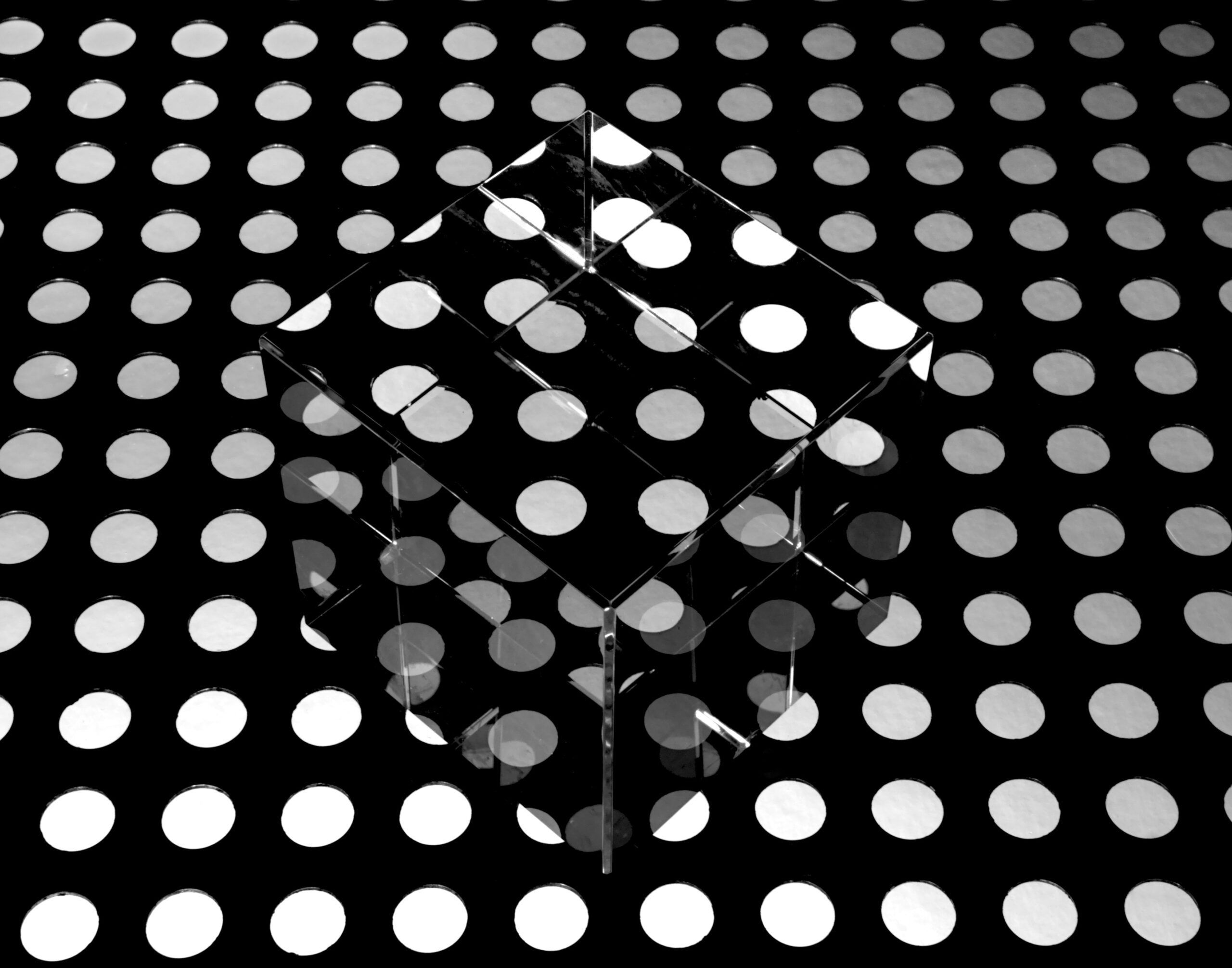物寂しさは漂うが、全編が優しいムードに包まれている。初出の1983年から35年経っているものの、古さはまったく感じない。話の途中に出てくる「ジョン・フォードの『リオ・グランデの砦』っていう映画を観たことある?」という台詞が、1996年の短縮版では『アパッチ砦』に変えられているようで、私が今回読んだのは改訂された短縮版の方だ。
この短編は、二年勤めた広告代理店を辞め、大学時代から付き合っていた女性とも別れ、祖母の葬儀のために帰郷した「僕」の一人称で書かれている。僕は中学生のいとこを、耳の治療のためにバスで病院へと連れていく。いとこは、右の耳に野球のボールをぶつけられ、聴力障害を抱えている。病院へ行くバスは、高校時代に僕が通学で使っていたバスだ。その日は、近くに登山ルートなど無いのに、なぜかリュックを背負った老人たちでバスは混んでいた。病院へ着き、いとこの診療が終わるまでの時間、僕は食堂でコーヒーを飲みながら待った。高校二年の夏休み、友達と一緒に、友達の彼女が入院する海岸近くの小さな病院へ見舞ったときのことをふと思い出す。彼女は長い詩を書いていると話していた。丘の上に小さな家があり、その家で女がひとりで眠っている。めくらやなぎという架空の樹があり、その花粉をつけた蝿が耳から入り込み、女の肉を内側からむしゃむしゃと食べたという。眠る女性を救うために、一人の若い男が丘をのぼっていくが。。。いとこが診療を終えて戻ってきた。食堂で昼食をとり、病院の門の前のベンチで帰りのバスを待つ。そこで、いとこはジョン・ウェインの映画の台詞「大丈夫です。閣下がインディアンを見かけたということは、つまりインディアンはそこにいないということです」を知っているかと僕に聞いてきた。いとこは、耳のことで誰かに同情されると、なぜかその台詞を思い出すという。僕は、あの夏の午後、お見舞いに持って行ったチョコレートのことを思い出していた。不注意と傲慢さによって、べっとり溶けて形を崩したチョコレート。そのことについて何かを感じるべきだった、つまらない冗談を言い合うのではなく、もっと意味のあることを言うべきだったと悔やむ。
という話だ。
著者らしく、いくつものメタファーが散りばめられている。(狙ってそうしているのかはわからないが、そういう気がする) バスの老人たち、ジョン・ウェインのセリフ、溶けたチョコレートetc、それらが何を意味しているのか、ここで分析しようとは思わない。それはすでに多くの人がしていることだし、あまりそうした謎解きは得意でも好きでもない。静かに迫ってくる死、避けることのできない病の恐怖などがテーマに思えるが、それよりもいとこへの優しさの方が印象として強く残った。それと、友達の彼女のことを思い出す優しさも感じた。死の暗示に溢れた重い話と見る向きが多いようだが、個人的には想像力(優しさ)の大切さを描いたポジティブな話に思え、読後感は悪くなかった。
これまでに何度か読み返しているが、改めてクオリティが高い短編だと思う。世界のMurakamiになるのはやはり必然なのだろう。