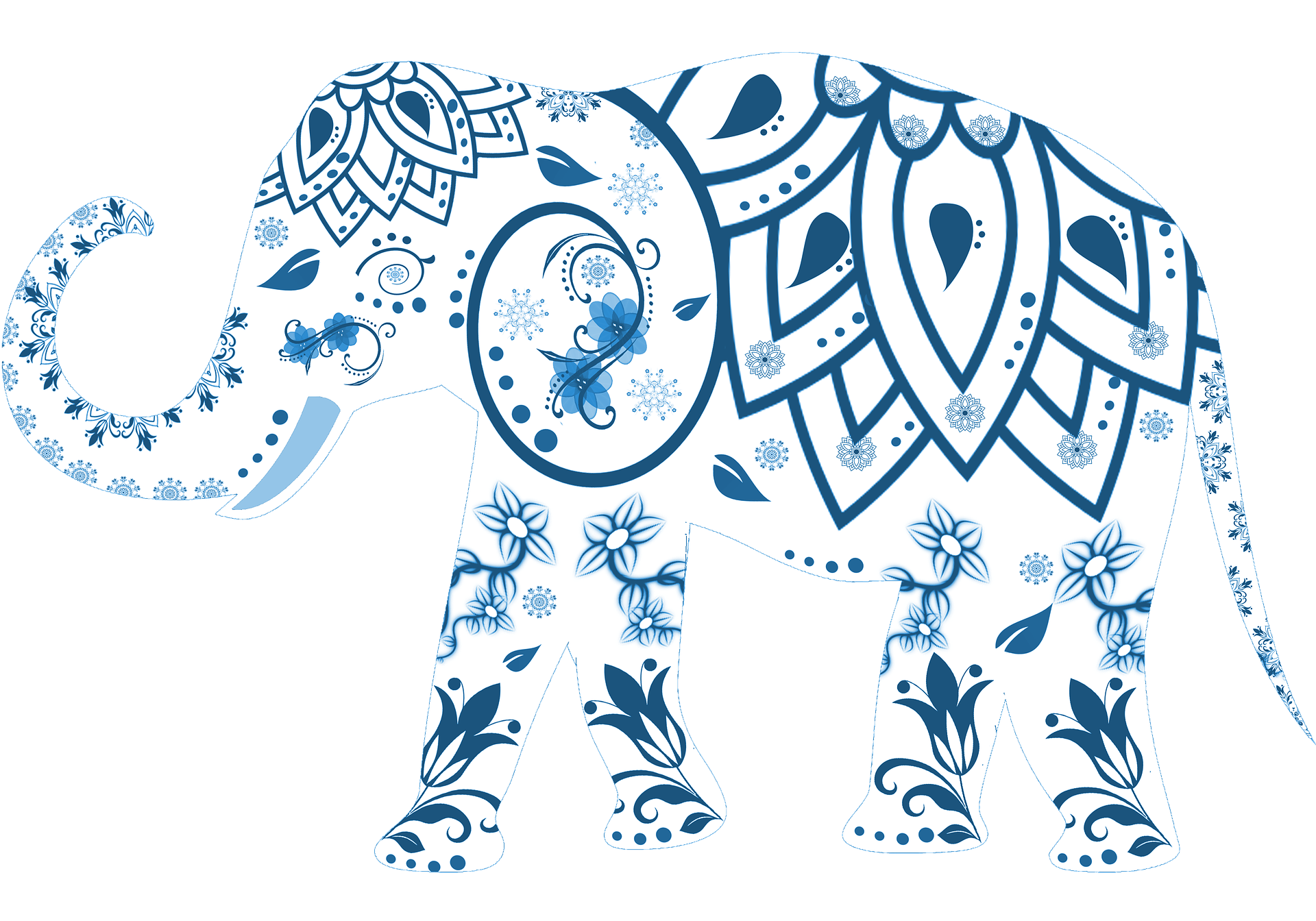「手品」は、オランダの作家トーン・テレヘンによる掌編小説集「おじいさんに聞いた話」に収められた一篇だ。
トーン・テレヘンを知らない?
大丈夫、実は私もよく知らない。オランダ国内では、動物を主人公にした児童文学や絵本で広く知られる国民的作家であるらしい。元々本業は医師であり、夏季休暇中に執筆するという暮らしを長く続けてきたそうだ。(これだけの情報でも落ち着いた大人の作家という印象を受ける) 他の動物たちとうまく付き合えないネガティブなハリネズミを主人公にした「ハリネズミの願い」は、本屋大賞の翻訳小説部門で一位を獲得し、日本でもベストセラーになっている。ファンも多いようで、谷川俊太郎や江國香織も愛読者とのこと。
「手品」の収録された「おじいさんに聞いた話」という短編集は、その邦題のとおり、祖父から聞いたロシアの話という体裁をとっている。ネタバレになってしまうが、実は一部の情報を除いて、基本的に物語は著者による創作であるとのこと。このあたりに著者の遊び心というか、いたずら心を感じる。「読者を騙して、これは詐欺だろ」と怒る人はまずいないだろう。
医者であり、童話作家であり、いたずら好きであり、「おじいさんに聞いた話」とくれば、ほっこり心あたたまる物語をイメージしてしまうが、そこはちょっと違う。ちょっと違うというより、かなり違う。文庫の帯のコピーにも・・・
「ハッピーエンドのお話はないの?」
「これは、ロシアのお話だからね」
ロシア生まれの祖父は、祖母にいくらとめられても
死をめぐる話、人生の悲惨と理不尽を
<ぼく>に語りつづけたー。
と書かれている。おじいさんから孫へというだけに、文体は穏やかで優しい。でも、語られる物語は暗い。そのギャップが特徴であり、「手品」も例外ではない。
祖父の話では、毎年十二月の聖ニコラウスの日、宮殿では皇帝一家のために手品師による公演が行われていた。ニコライ・グリーンという手品師が、布をかぶせてネズミをゾウに変えてしまうという驚愕のマジックを披露したところ、皇帝一家はいたく気に入った。客人にいつでも見せられるよう、手品師は故郷に帰ることを禁じられ、家族から離れて暮らす日々の中でやつれていく。故郷に帰してほしいと何度も懇願するが、許可は下りない。第一次世界対戦が勃発すると、低下した軍の士気を高めるため手品師は前線に送られてしまう。何度も何度も繰り返し兵士の前で手品を見せるニコライ。しかし、ネズミをゾウに変えるより、俺たちを手品で家に返してくれと兵士たちに嘆かれるばかり。前線に来て二週間が経った頃、狙撃兵の銃弾を受け、手品師は命を落としてしまう。暗闇の中、森へと逃げていく亡霊のようなゾウを見た者がいたらしい、と祖父は話す。
なんとも救いのない話だ。権力者に自由を奪われ、家族と再会する夢も叶わぬまま死を迎える憐れな手品師。帯に書かれているとおり、人生の悲惨と理不尽がそこに描かれている。「おじいさんに聞いた話」というやわらかな字面や表紙のイラストを見て、ハートウォーミングな世界を予想していた読者は裏切られることになる。。。
トーン・テレヘンの作品を読むとき、先入観とのギャップをどう捉えるか、ここが評価の分かれ目になる気がする。(ネット上のレビューでは割と好き嫌いが二分している)
「幸せな気持ちになれる温かな話を期待していたのに・・・」とガッカリするか、「穏やかな語り口の中に人生が描かれていて心に染みる」と受け取るか。
どちらかというと、私は前者かもしれない。上質で深みのある短編だとは思うのだが、穏やかなトーンで恐い話をする人が、なんとなく昔から苦手だ。以前、上司にそういうタイプの人がいて、不気味に思えてしまい、トラウマになっている。人も小説も映画も音楽も、私はフィジカルでストレートなのものの方が基本的に好きだ。例えば、映画だとミュージカルが好みだったりする。楽しくて思わず踊りだす、嬉しくて思わず歌い出す、こういう単純な力強さに惹かれる。劇場で観た世代ではないが、「雨に唄えば」や「ウエストサイド物語」は理屈抜きに最高の映画だと思う。
まあ、これはあくまで好みの問題で、作品のクオリティ云々の話ではないので誤解のないよう。ファンの方は気を悪くしないでいただきたい。