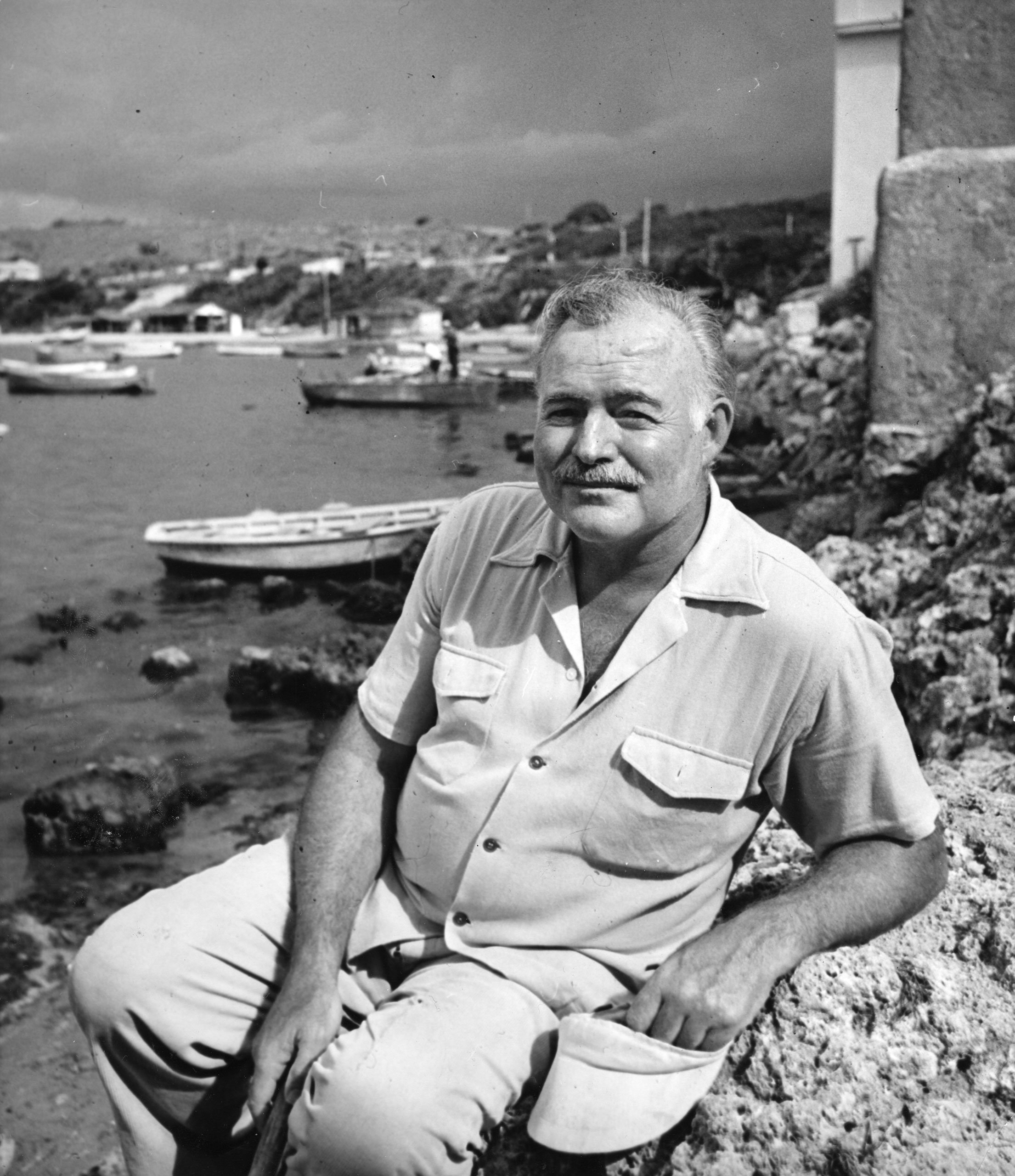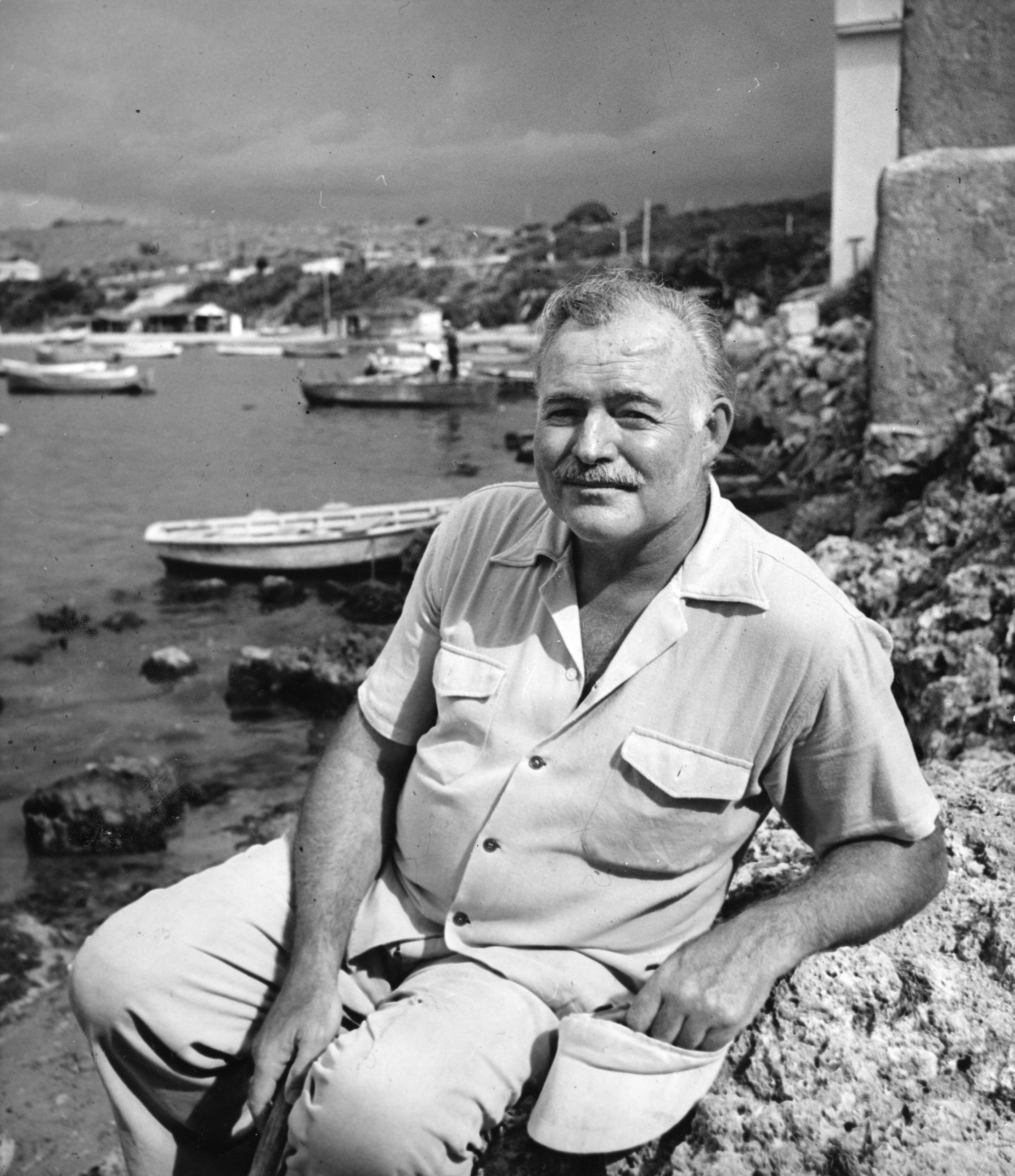ヘミングウェイの作品はどれも徹底的に推敲を重ね、細部まで丁寧に書かれている。とても丁寧に書かれているので、大切に大切に読みたくなる。
「死ぬかと思って」(原題:A Day’s Wait)は、子どもの無邪気さを描いたシンプルなスケッチ的作品に映るかもしれないが、そこはヘミングウェイ。いろいろと練りこまれており、短いながらも多面的で奥行きのある作品になっている。
あらすじ:
息子がインフルエンザに罹り、熱を出してベッドに寝ている。それを見守る父親。海賊の本を読み聞かせようとするが関心を示さない。眠ろうともせず妙な表情を浮かべてベッドの脚元を眺めている。面倒ならここにいなくていい、と息子は父に言う。父親はアイリッシュセッターをお供にウズラを撃ちに出かける。二羽仕留め、愉快な気分で家路につく。息子は外出前とまったく同じ姿勢でベッドの脚元を眺めている。もう一度、海賊の本を読み聞かせようとするが、やはり聞く気がない。「ねえ、ぼくはいつ頃死ぬのかな」と訊いてくる息子。何故そんなことを質問したのか問うと、華氏と摂氏を勘違いし、体温100度だから自分は死ぬと心配していたことがわかる。
作中で息子に読み聞かせているのは、ハワード・パイルの海賊の本だ。「ロビン・フッドの冒険」だろうか。「ロビン・フッドの冒険」は、虐げられた人々のために悪政に反抗した英雄の話である。イギリスのシャーウッドの森に住むアウトローの首領で、1241年没という伝承もあるが実在した証拠は何もない。つまり、架空の英雄だ。ヘミングウェイはこの短い物語の中で、二度も「海賊の本」に息子が無関心である描写を入れている。これは、人が「死」に直面している時(あるいは「死」を強く意識している時)、絵空事や作り話などは何の役にも立たないということを暗に表しているようにも思える。ヘミングウェイという作家はご存知の通り、経験したことや熟知していることをベースに小説を書く。いかにもな作り話を嫌っていたのではないだろうか。
*追記:後で気づいたのだが「海賊の本」と言っているのだから、おそらく「カリブの海賊」かと思う。「ロビン・フッドの冒険」などと見当違いのことを書いてしまい恥ずかしい。。。完全に私のポカです。ただ、ヘミングウェイと違ってパイルは史実を重視しないタイプの作家だったようなので、虚構のメタファーとしてパイル作品を使ったのかもしれない。あまり自信はないが。
もう一つ。高熱で寝込む子どもを置いて父親が狩りに出かけるのは不自然な行動に思える。子どもは、面倒ならここにいなくていい、と繰り返し父に言う。これも謎めいている。華氏と摂氏を勘違いしていることから、この子がアメリカ育ちではないことが推測できる。ヘミングウェイがパリにいた頃に生まれた子どもが、アメリカに泊まりに来ているという状況であれば腑に落ちる。母親が登場しないのも、その家にいるのは後妻であり、子どもの実母でないためか。そう考えると、面倒ならここにいなくていい、という息子の言葉からは切ない気遣いを感じ取れる。
でも、なぜウズラ撃ちに行ったのか?ただの息抜きなのか。たとえそれほど心配のない病状であったとしても、我が子が苦しんでいるときに愉快な気持ちで引き揚げてきたことも解せない。息子が抱く死への不安感を浮き立たせるための手法とも思えるが、どうなのだろう。
原題のA Day’s Waitは邦題と違って「死」という言葉を使っておらず、「一日待つ」という想像を掻き立てる暗示的なタイトルだ。一日経つとすっかり気分が変わっている、子どもはそういう単純明快な生き物ってことなのかな。
勝者に報酬はない・キリマンジャロの雪―ヘミングウェイ全短編〈2〉 (新潮文庫)