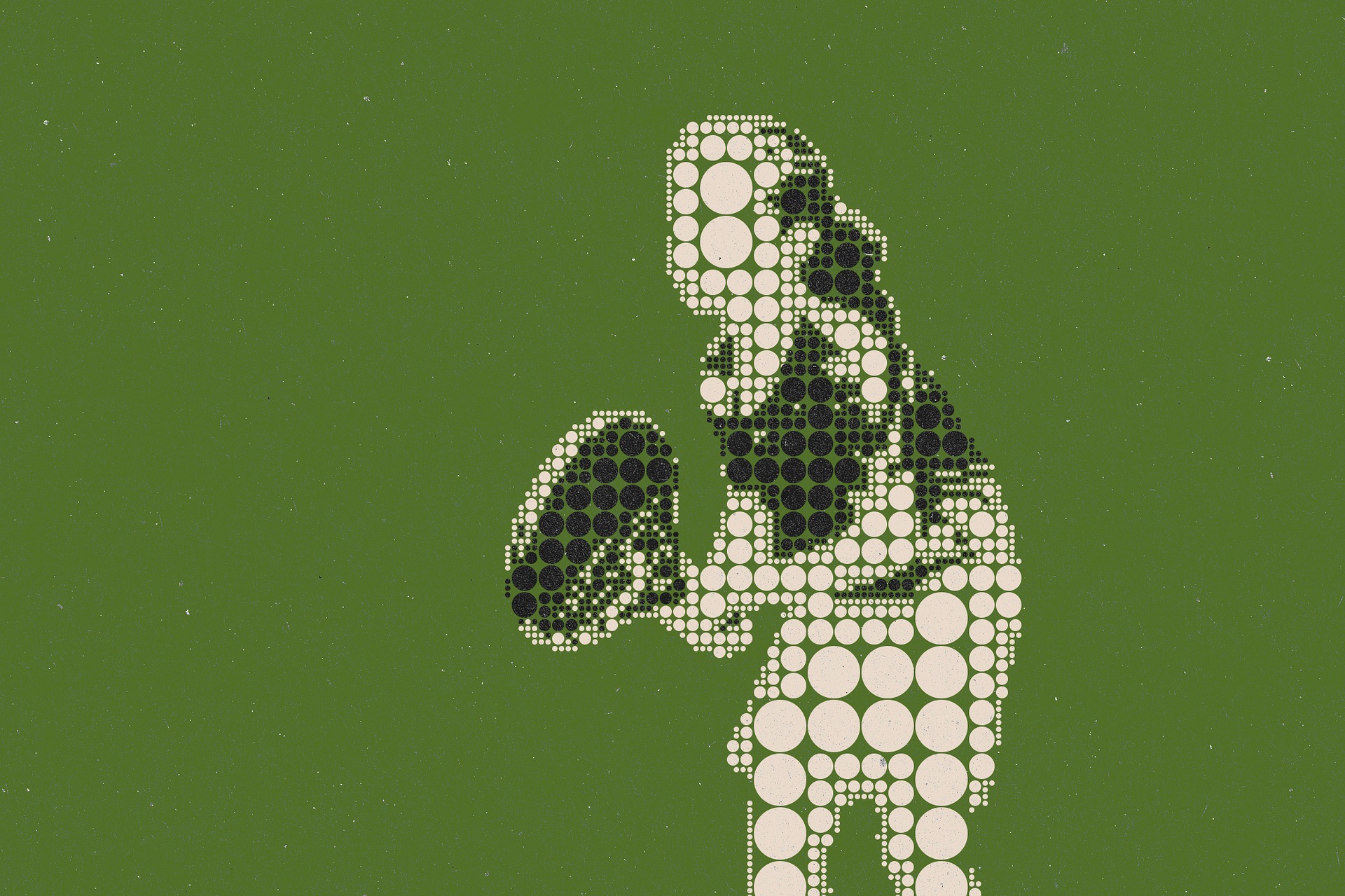「小舟のほとりで」(原題:Down at the Dinghy)は1949年に「ハーパーズ」4月号に掲載された短編で、数年して短編集「ナイン・ストーリーズ」に収められた。70年近く前の作品とは思えないほどフレッシュな一篇で、繰り返し読みたくなる魅力に満ちている。
閉鎖的と呼べるほどに内向的でナイーヴ、それが私のサリンジャーに対してのイメージだ。ヘミングウェイよりフォークナーに近く、積極的に社会にコミットしていくタイプとは思えない。要塞に閉じこもり、道徳的に汚れのなかった子供時代のpurenessを守り続けている、そんな作家に思える。あまりサリンジャーに詳しくないので、誤解しているかもしれないが。
「小舟のほとりで」のあらすじは次の通り。(ウィキペディアより)
メイドのサンドラは近所に住むスネル夫人と心配事があると会話している。そこに女主人のブーブー・タンネンバウムが現れ、「家出」したという4歳の息子ライオネルの居場所を聞く。
ライオネルは父親の小舟に座っている。やってきたブーブーは家出の理由を聞くが、ライオネルは答えず舟にあったゴーグルを湖に投げ捨てる。ブーブーはプレゼントのキーチェーンをライオネルに見せ、これも捨ててしまったほうがいいかと言う。そしてキーチェーンをライオネルに投げるが、ライオネルはそれも湖に投げ捨ててしまい、泣き出す。そして、サンドラがスネル夫人に、父親のことを「薄汚いユダ公(カイク、Kaike)」と言ったのを聞いたことが家出の理由だと告げる。ブーブーはライオネルを慰めるが、「カイク」の意味を尋ねると、ライオネルは「空に上がる凧(カイト、Kite)」だと答える。泣き止んだ息子と母は二人で家まで走って競争する。
子どもへの柔らかな眼差し、ドキュメンタリーを思わせるナチュラルな展開、一枚の絵画のように美しい情景、それらが高いところでひとつに溶け合った名作だと思う。明るい話では無いが、読後感は悪くない。
この短編はユダヤ差別がテーマとよく言われる。差別する側とされる側の描写を前後半で分けたような構成になっており、両者のコントラストが印象に残る。何気ない陰口の残酷さが、傷ついた子どもの心を通して読み手にリアルに伝わってくる。感情に流されない母親ブーブーの抑制の効いた言葉には、逆にやる瀬なさを感じて辛くなったりもする。ただ、著者はこの短編で差別の実情を社会に訴えようとした訳ではない気がする。これは私見だが、想像力の有る人と無い人を、個人的な差別体験を元に描き出そうとしたのではないだろうか。「世の中には二種類の人間がいる、想像力の有る人と無い人」と思って普段生きているので、こじつけてそう感じているだけかもしれないが。。。
翻訳の好みについていろいろ意見が分かれているようだが、原文で読むと魅力が増す作家という気がする。ネタバレにはなるが、締めの短文が見事に決まっている。
they raced. Lionel won.