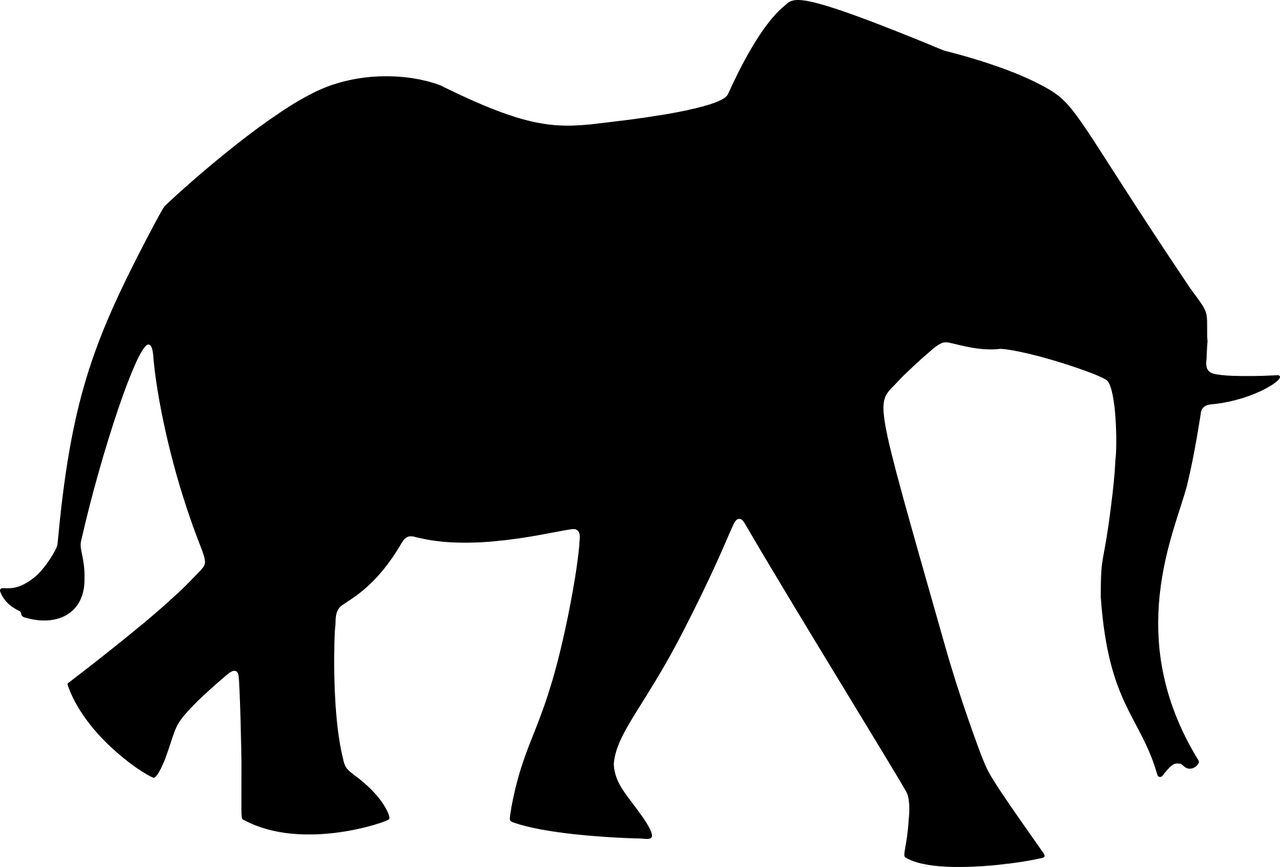著者が40代前半、1991年に書かれた短編だ。1991年は、新都庁が完成し、Jリーグが発足し、宮澤内閣が誕生した年だ。
天候不順により飛行機のフライト時刻が遅れている。空港のレストランで、「僕」は仕事の先輩である大沢と運航再開を待っている。大沢がボクシング経験者であることを意外に感じ、「これまでに喧嘩をして誰かを殴ったことはありますか?」と訊ねてみる。大沢は、中高生時代の一人の同級生との逸話を語り始める。
という話だ。
随分と簡単にまとめたと思われるかもしれないが、このブログではあまりストーリー紹介に力を入れないことにしている。読後に見ている人が多いと思われるのと、筋を詳しく紹介することで未読の方にとって鮮度が下がってしまうし、ネタバレにもなってしまう。あらすじで、記事の文字数を稼ぐみたいなこともしたくない。
10年前だったか20年前だったかは覚えていないが、「沈黙」は私が初めて読んだ村上春樹の短編だ。先輩の大沢の話がまるで自分のことのように思え、深いところで重たい衝撃を受けたのを覚えている。暗くて孤独な中高生時代を過ごした自分にとって、教室内の陰湿な空気に耐える日々は他人事ではない。今回再読して、以前とまったく同じ嫌悪感や怒りが湧きあがってきた。
悪意を持ち、人の心を巧みに掌握して扇動する狡賢い人間。そして、それに無批判に従う無表情な連中。そうした集団に溶け込むことができなければ、どれほど不利な立場に置かれることになるのか。流れるようなスムーズな文章で、いじめの世界を描き出している。
どこかで村上春樹は次のようなことを書いている。
「物語を作るというのは、自分の部屋を作ることに似ています。部屋をこしらえて、そこに人を呼び、座り心地のいい椅子に座らせ、おいしい飲み物を出し、その場所を相手にすっかり気に入らせてしまう。そこがまるで自分だけのために用意された場所であるように、相手に感じさせてしまう。それが優れた正しい物語のあり方だと考えます。」
「沈黙」は心が躍るようなファンタジックな話ではないが、読んでいて自分だけのために用意された特別な場所に思えた。その淀みのない滑らかな文章は、内容に関わらず読み手をいつでも心地好くさせてくれる。本篇は、他の作品に比べてメタファーが控えられており、個人的にはとてもナチュラルに、とてもストレートに心に入ってきた。
この物語のモチーフはいじめであり、悪意に面と向かって対峙するのではなく、超然といなす心の有り様を教えてくれる。学校にすっかり希望を失い、日々耐えながら過ごしている子どもたちの力になる短編だと思う。