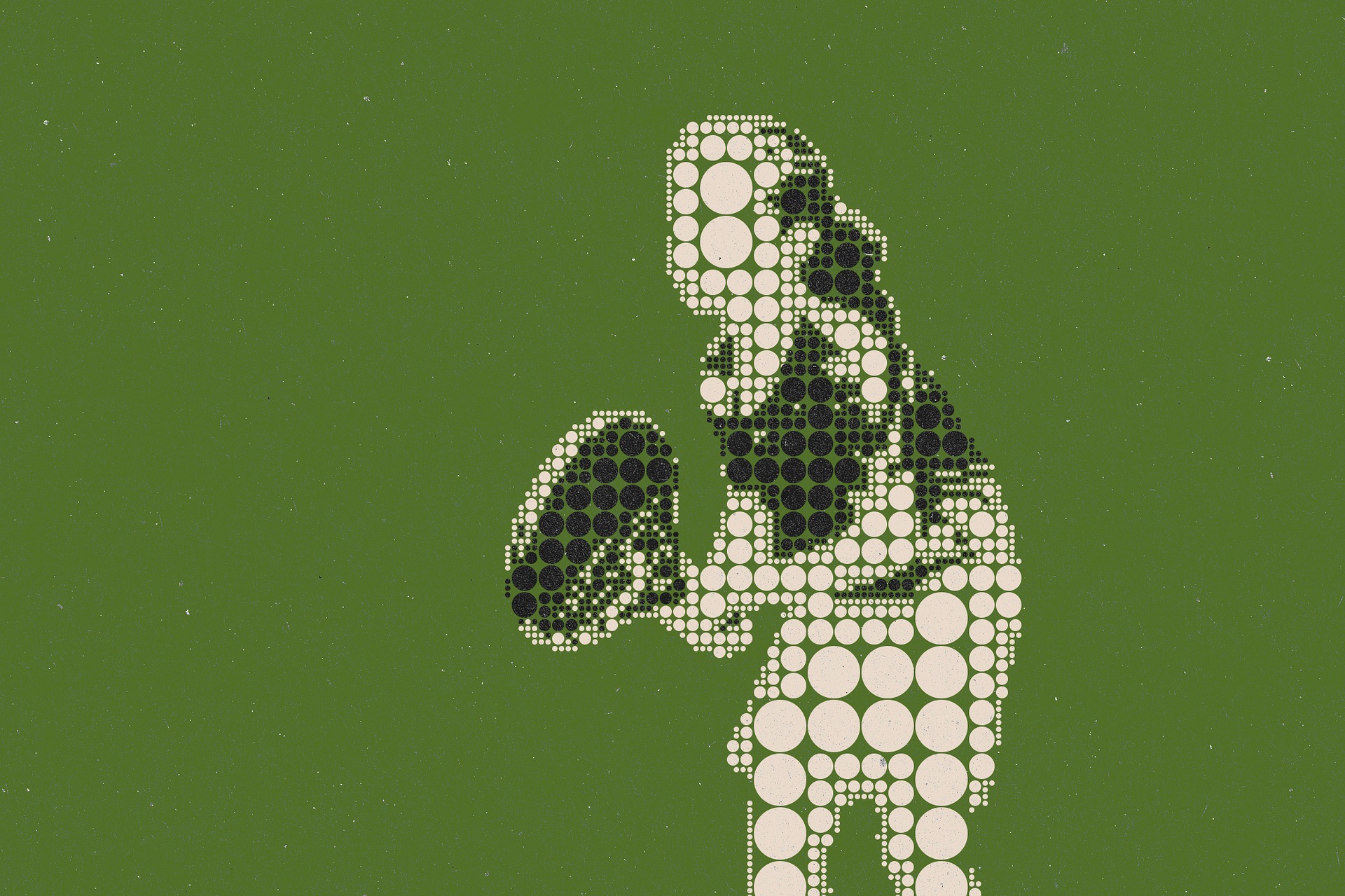原題はUncle Wiggly in Conneticut。短編集「ナイン・ストーリーズ」に収められた短編だ。なんと1949年に映画(邦題「愚かなり我が心」)になっている。 自作の映像化を嫌うイメージが強い作家なので、映画化を許したこと自体に驚いた。(これで凝りたのかな?) 作品の出来は今一つだったようで、批評家の評価も芳しくなかった。サリンジャー本人も「ハリウッドでひどいめに遭った」と嘆いていたらしい。
小説の話をしよう。まず、この短編はタイトルで少し損をしている気がする。読後には納得できるのだが、「コネティカットのひょこひょこおじさん」からイメージされるようなハートウォーミングな話では全然ない。(ひょこひょこおじさんが悪いタイトルと言わないが、個人的にはあまり読書欲をそそられないかな)
どういった話かというと、同じ大学を中退した元ルームメイトの女性二人による会話劇だ。全体の8〜9割がダイアローグである。一人は結婚して、夫と娘を持つ。もう一人は独身で仕事を持つ。二人ともアメリカのどこにでもいるような中流階級の女性で、話題は学生時代の思い出やちょっとした愚痴。リラックスした姿勢で、ハイボールを飲み、タバコを吸いながら、ティーンのような口調で他愛もない会話をダラダラ続ける、という内容だ。
とは言っても、そこはサリンジャー。何気ない会話や行動が示唆に富んでいて、読み手のセンシティビティを問うてくるような奥行きがある。細部の細部まで、緻密に練られている感じだ。
妻子ある女性の方は、この世を去った昔の恋人のことで頭がいっぱいだ。彼女の一人娘は空想の世界にどっぷり浸って生きており、そんな娘にうんざりしている。その夜、娘をきつく叱りつけた後、彼女は真っ暗な部屋の戸口で長いこと佇んでいた。自身の不遇と娘の孤独を重ね合わせたのだろうか。それまで無関心であった娘に対し、涙とともに愛情が湧き上がってくる。このシーンは、読んでいてとても心を揺さぶられた。 ただ、これはあくまで私の解釈ではあり、皆さんの感じ方と違うかもしれない。できれば前向きな話と解釈したいが、エンディングは自己肯定感に欠けたものに思えるし、独身女性の方が既婚女性の夫に好意を抱いているようにも取れるし、正直よくわからない。。。
とにかく、丁寧に綿密に書かれている。例えるなら、超高精細なモニターでくたびれムードのホームドラマを観ているような感じだ。なんというか、ややオーバースペックとも感じる鮮やかさがある。どちらかというと私は骨太な作風が好きだが、それでも一流の技巧派作家に今回もすっかり酔わされてしまった。サリンジャーは、やはりサリンジャーである。