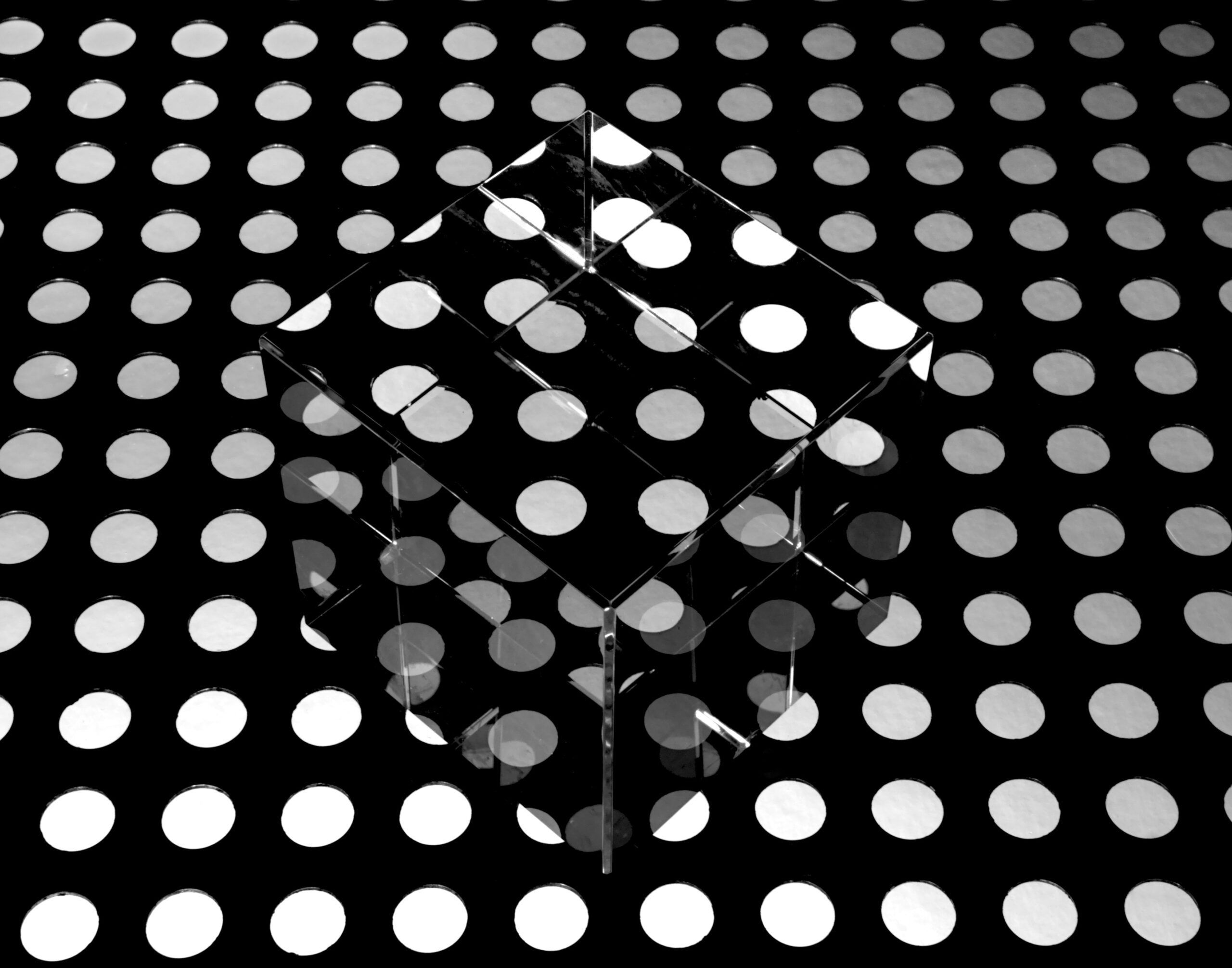2018年7月号の「文學界」に、村上春樹の最新短編3作「石のまくらに」「クリーム」「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」が同時掲載された。(2020年の夏に、6年ぶりの短編小説集「一人称単数」として刊行されている)
今回の記事は「石のまくらに」を読んでの感想。
物語は回想として語られる。主人公の「僕」が作家志望の大学生だった頃、アルバイト先で知り合った年上女性と一夜を共にした。彼女が短歌を詠むことに「僕」が関心を示すと、自作の短歌集を郵送してくれた。現在、彼女が生きているかどうかさえわからないが、その短歌集を今でも「僕」は読み続けている。
新作なのであまり詳しくは書かないが、ざっくりこういったあらすじだ。物語の設定もそうだが、語り口にもハルキ節は健在で、性的な描写が多いあたりも著者らしい。(アンチの人には受け入れ難いかもしれないが)
ただ、これまでの小説とは何かが違っている気がした。それは物語が進行する速度のような気もするし、作品全体を包むトーンなのかもしれない。いつものような非現実的な謎は影を潜め、どこか私小説風でもある。著者には珍しく短歌という伝統的な和の文化を題材にしていることも、作品の味わいに影響しているのかもしれない。
良し悪しは別として、老いの匂いが漂っているようにも感じられた。著者は満69歳、老いる年齢ではないので、円熟味や深淵さを増したといった方が正しいだろう。文芸誌でなく、文庫で読めばまた違う印象を受けるのかもしれないが。
短編として面白いか、面白くないか? なんだか、もうそういうことではない気がした。小説一筋でやってきた人が出す妙味を堪能できる、それだけで充分という感じだ。
名前も知らない、顔もよく思い出せない、人生のある地点でいっときの出会いを持っただけの女性が書いた短歌。それが、長い年月を経た今も「僕」の心に確かに存在している。瞬く間に人は老いて、滅びへと向かう。肉体は後戻りできず、残るのはささやかな記憶だけ。自らの身も心も無条件に差し出すことで、わずかな言葉だけが誰かの胸に残り、他はすべて塵と消えてしまう。「僕」は、死のイメージを追い求める短歌を詠んだ彼女が、今もどこかで生きていて欲しいと願っている。
この物語の中で、小説家・村上春樹は自身の創作人生を振り返ったのかもしれない。誰かの胸にわずかな言葉を残すために、自分自身を差し出して生きてきたことへの矜持をそこに感じた。たとえ、たった一人にしか届かなかったとしても、それは充分に価値ある創作なのだと自らを讃えているように思えた。
この短編を読み終え、私は次のフラナリー・オコナーの言葉を思い出した。
「小説を書くことは現実のなかに突入することであって、全身に強烈な衝撃を受ける。もし小説家が金銭的な希望によってささえられないならば、神の救いという希望によってささえられなければならない。そうでなければ小説家がこの試練を生きぬくことは全く不可能になるだろう」