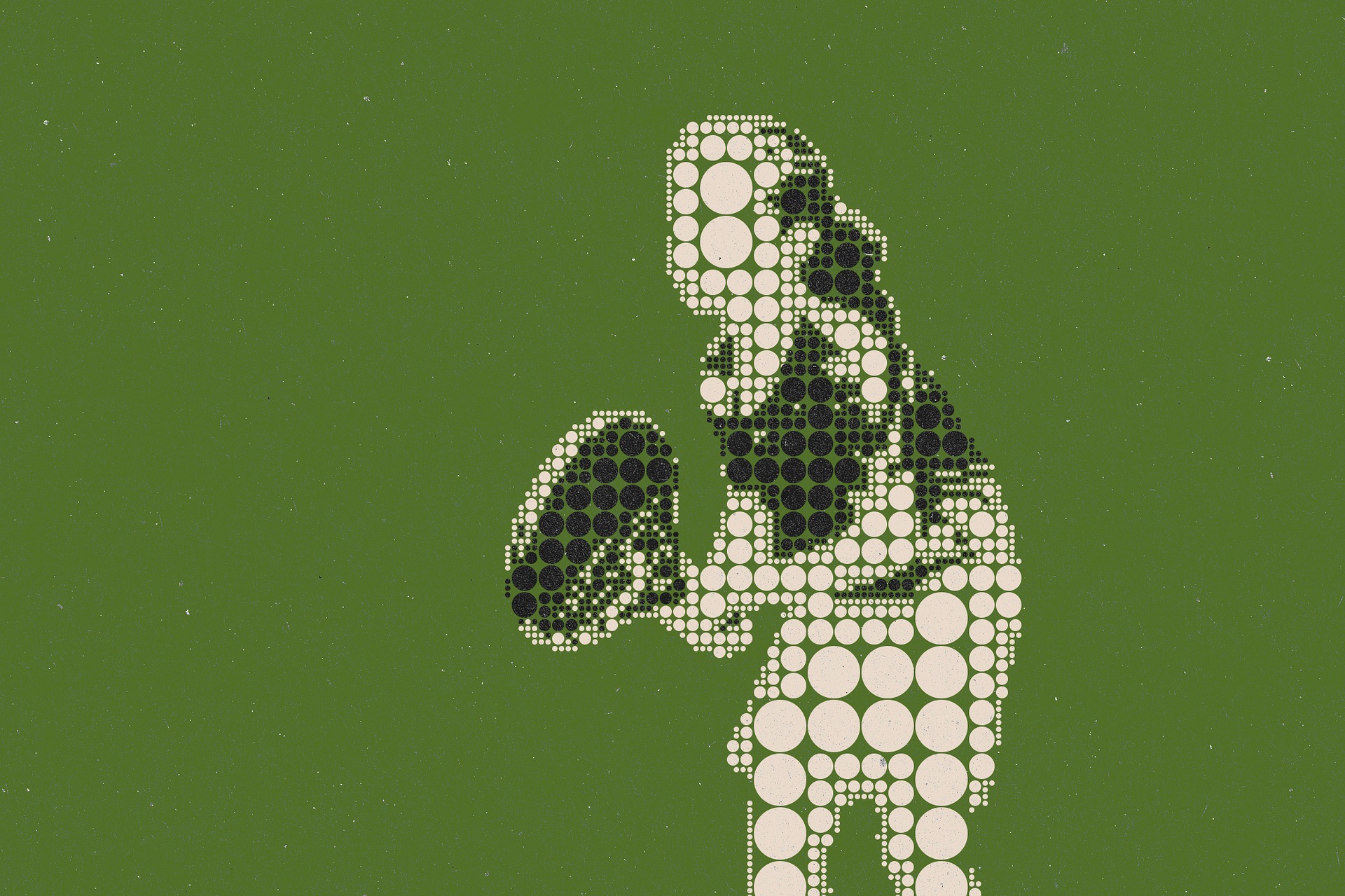「バナナフィッシュにうってつけの日」や「バナナ魚日和」などの邦題で知られる短編A Perfect Day for Bananafishは、1948年の「ザ・ニューヨーカー」誌に掲載された、サリンジャーが注目されるきっかけとなった重要な作品だ。ちなみに同年の日本では、美空ひばりがデビューし、太宰治が入水自殺している。後に「カンガルー日和」を執筆する村上春樹はまだ生まれていない。
あらすじはというと(*ネタバレ注意!)
ミュリエル・グラース夫人が海辺のホテルでニューヨークの母親と電話で話している。母は、娘の夫シーモアが自制力を失っておかしな真似をしないかと心配で仕方がない。夫のシーモアは砂浜に寝ている。同じホテルに泊まっている幼い女の子シビル・カーペンターと会話を交わし、バナナフィッシュをつかまえるために二人で海へ入る。バナナフィッシュとは、バナナが入っている穴へ入っていく魚だとシーモアはシビルに説明する。バナナを大量に食べたバナナフィッシュは穴から出られず死んでしまうとも。波に襲われた時、シビルはバナナフィッシュが一匹見えたとシーモアに伝える。ホテルへ戻る途中、エレベーターに同乗した女性に対し、シーモアは妙なクレームをつける。そして、宿泊する部屋のベッドで、眠る妻の横でこめかみを撃って自殺する。
かなり有名な作品なので、衝撃的な結末もご存知の方が多いことだろう。陸軍がシーモアを退院させたことが間違い、といった医師の見解を母親が話すシーンがあり、戦争体験による精神障害が自殺の原因と思われる。
解題はここまで、以上。
投げ出すわけではないのだが、多くの研究者やファンの間ですでに分析し尽くされているので、サリンジャーのファンでもなく、浅い知識しか持たない自分が何か言える気がとてもしない。「シーモアの宿泊する部屋が507号室で6が無いからsixlessで、それはsexlessの暗示である」のような解釈を聞かされると、物怖じして自分の見解を言えなくなってしまう。私はあまり謎解きを楽しむタイプではないので、割と早い段階でお手上げと諦めてしまうところがある。小説ではないが、デヴィット・リンチの映画がちょっと苦手だったりする。ハマる人の気持ちはわかるが、あそこまでミステリアスだと思いを巡らす前にギブアップしてしまう。「バナナフィッシュにうってつけの日」は、言うほど謎めいていない気もするが、バナナフィッシュという架空の生き物が登場した時点で、急に思考がオフになってしまった。。。
話がよく見えなくなってきたが、精巧な美術品のような短編であるとは思う。バスローブを着たままビーチに寝る。幼い子どもを相手に比喩に満ちた話をする。エレベータで女性に言いがかりをつける。無垢さや清純さの喪失に過敏な心を、私欲にまみれた社会への幻滅を、これほどデリケートに美しく描ける作家はそうはいない気がする。そこには緻密な計算と執拗なまでの推敲があるのだろうが、他の人には些細に思えることにも徹底的にこだわる姿勢の凄みを感じた。
サリンジャーのエージェントは翻訳に対してかなり厳しいらしく、原題に忠実な邦題を付けさせ、序文など書き加えもNGとしているそうだ。そもそもサリンジャーがザ・ニューヨーカー誌と契約を結んだのも、著者の同意抜きに作品に手を加えない雑誌であったかららしい。(まあ、作家の多くは改変には神経質とは思うが) そうした職人気質の強い技巧派作家が妥協無しに書いたのだから、細部まで研究する読者が多いのは自然なことだと思う。「ライ麦畑でつかまえて」など他の作品を読み込むことで、この短編への考察は深まる気もするが、今の私では解題には力不足だ。まとめの言葉が見つからないので、中途半端な感じが残るが、今回はこれでお許しいただきたい。。。